【飲食店】YouTubeを用いて集客する方法とは?コツや成功事例についても解説!

「YouTubeを使って集客したい」
「YouTube運用の方法が分からない」
飲食店を経営している方の中で、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
近年では、SNSの普及に伴いSNSを集客に用いている企業や経営者が増えています。
本記事では、飲食店を経営している人が集客を目的としてYouTubeを始めるメリットやコツについて成功事例を交えて解説します!
飲食店がコストをかけずにYouTubeでの宣伝を成功させるコツが詰まっているので、チャンネルを持っている方や、これからYouTubeを始めようと考えている方はぜひ参考にしてください。
YouTube(ユーチューブ)の運用代行に関して、相場や運用代行の概要を以下の記事でまとめています。詳しく知りたい人はぜひ合わせてご覧ください。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のYouTubeを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたらフォームよりお問合せください。
飲食店がYouTubeを活用するべき理由

飲食店がYouTubeを活用することで、全世界の若年層だけでなくシニア層までも、幅広い世代への認知度拡大が可能です。また、地域に縛られないマーケティング活動が可能なため、商圏外の需要や、さらに言えば海外需要を取り込むことさえ期待できるでしょう。
YouTubeは、2022年7月時点で世界20億人が使用していつ世界最大の動画視聴型SNSです。また、日本国内の月間アクティブユーザー数は2023年5月時点で7,120万人を超えています。ユーザーも幅広く若年層からシニア層に至るまで全世代をとおして人気のSNSです。
また、「食」は人間の三大欲求の一つであり、YouTubeにおいて老若男女問わず人気のコンテンツです。実際、YouTubeの人気コンテンツの調査によると、グルメ系の動画の人気は上昇傾向にあります。なかでも昨今注目を集めるYouTubeショート動画との相性が非常にいいのが特徴。
YouTubeショートは1日で700億回を超える再生数を誇っており、うまく活用することで認知度を一気に高められることに加え、収益化も狙えます。
YouTubeで料理動画が人気を集めている背景には、コロナ禍のおうち時間によって、自炊に興味を持つユーザー層が増えたことが挙げられます。コロナが明けた現在においても引き続き料理動画からアイデアを求めるユーザーが多いことが予測できるでしょう。
また、「飯テロ」などという言葉が誕生しているとおり、人々の食欲を一瞬で掻き立てるような印象深い投稿も、引き続き人気を集めています。
飲食店がYouTubeを運用することで、あらゆるターゲットへアプローチができ、商圏外からの顧客獲得も期待できるでしょう。競争の激しい飲食店業界だからこそ、ユーザーの「行ってみたい」、「食べてみたい」といった欲求を引き起こすことが重要です。
飲食店がYouTube運用を行うメリット

実際、YouTubeを飲食店の集客に用いる事で、さまざまなメリットがあります。うまく取り入れて、集客に繋げましょう。
広告費用をかけずに宣伝ができる
YouTubeは初期費用があまりかからないため、看板広告やWeb広告を出すよりも低コストで始めることができます。
高額な撮影機材や編集機材がなくても、スマートフォンが一台あれば動画を作成することが可能です。
また、自分で撮影編集が難しい場合でも外注することができ、看板広告やWeb広告よりもランニングコストを大幅に抑えることができます。
数年前の動画がきっかけで予約や問い合わせが来ることも少なくないため、継続して投稿し動画を増やすことが重要です。
表現がしやすい
YouTube動画は、看板広告やWeb広告よりも自由度の高い表現をすることが可能です。
制約が少なく創意工夫の余地が大きいため、視聴者が今すぐ食べに行きたくなるような「美味しそうな演出」をすることが可能です。
字幕やリアクションを用いることで、動画だからこそ表現できる臨場感を視聴者に伝えることができます。
店の雰囲気が伝わる
料理だけでなく店舗の雰囲気を伝えることができるのも大きなメリットの一つです。
看板広告やWeb広告では、動画コンテンツが少なく来店するお客さんからすると、店舗の雰囲気が分かりにくいという課題があります。
YouTube動画を用いてお店の雰囲気を伝えることで、視聴者は実際に来店した時のイメージを想像しやすくなります。
信頼感・安心感を与えられる
人間の心理的には正体がわかっているものに安心感や信頼感を抱きやすい傾向があります。
飲食店においても同じように、料理をしている姿だけでなくプライベートな側面も見せることで視聴者に親近感を抱かせることができます。
オフィシャルな媒体では中々見せられない裏側を見せることができるのは、YouTubeならではのメリットです。
広告収入が得られる
- チャンネル登録者が1,000人以上
- 直近12か月で動画の総再生時間が4,000時間以上
YouTubeでは、上記の条件を満たすことで広告収入を得ることができます。
簡単に達成できる条件ではありませんが、収益化できればお店の売上以外の収入源を確保することができます。
コロナ禍で多くの飲食店が収入を得られず廃業したことからも分かる通り、飲食店は複数の収入源を持っていて損はありません。
収益化に成功すれば、集客や宣伝をしながら収入を得ることができます。
飲食店がYouTube運用を行うデメリット

飲食店がYoutube運用を行うのには、メリットだけでなくデメリットもあります。
運用を継続していくのが現実的なのか、メリットと比較した上で検討してみてください。
編集技術が必要
Youtube運用をするには、編集技術が必要になります。ただ撮影をしたものを投稿するだけでは、ほとんど伸びることはないからです。
近年はYouTubeを活用している企業や経営者が多く、クオリティが成熟しています。動画編集にはある程度の専門知識が必要なため、飲食店経営と並行して動画編集を学ぶ必要があります。
一方で、飲食店は忙しいことが多く、動画編集の知識を得るのために使えるリソースが限られるでしょう。
そこでおすすめなのが、動画編集の外注化です。すでに知識やノウハウのあるプロに依頼することができます。また、動画編集にも流行があります。動画編集を外注することで、高いクオリティの動画を投稿することができるのは魅力といえるでしょう。
動画編集の外注は、クラウドソーシングサイトを使用して個人に依頼する場合と、企業に依頼する場合の2パターンに大別できます。
個人に依頼する場合には、5分ほどの動画で5,000円〜10,000円、企業に依頼する場合には、10万円以上となるケースが多いです。また、企画立案から撮影、編集までを含めると、10万円以上は覚悟しておくべきといえるでしょう。
個人に依頼する場合には、音の挿入のみやテロップのみなどの一部のみを依頼できるため、コストを抑えて必要な作業のみを依頼したい場合には、個人がおすすめです。
人件費がかかる
社内の人員だけでYouTube運用するのに限界を感じた時、YouTube担当者を採用する選択肢もあります。
しかし、YouTubeに精通した人を雇う場合、当然ある程度の人件費がかかってしまいます。
YouTubeは、社内の人員だけで行うことができれば費用を最小限に抑えることのできる媒体です。
YouTube運用の担当者を採用する場合その分の人件費が発生するため、飲食店の従業員以外の人件費が別途かかります。
さらに担当者が退職した際は社内にノウハウが残らず、YouTubeチャンネルの運用が不可能になるリスクもあります。
継続するのが難しい
YouTubeで集客を行う上で最も重要であり大変なことは、継続して投稿を行うことです。
近年ではYouTubeを活用している企業や経営者が多く、動画が増えているため再生数や登録者は増えにくくなっています。
数字が付いてこないと後回しにしがちですが、YouTubeは継続して投稿を行わない限り結果がでにくい媒体です。
社内でYouTubeの投稿を継続することが難しい場合、運用代行サービスを利用するのも一つの手段です。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のYouTubeを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたらフォームよりお問合せください。
飲食店のYouTubeを伸ばすためのコツ

では実際にYouTubeを飲食店の集客に活用する際に何に気を付ければいいのでしょうか。
ここでは作成する際に意識するべきことを6つ紹介します。
①ターゲットを明確にする
動画を作成する際には、誰に何を伝えたいのかを明確にするようにしましょう。
1つの動画に様々な要素を詰め込みすぎると何を伝えたいのかが分からない動画になってしまいます。
1つの動画で伝えるテーマは1つに絞り、訴求したい相手に訴求したい内容がしっかりと伝えられるよう意識しましょう。
YouTubeの企画の考え方についてはこちらの記事を参考にしてみてください!

②視聴者の食欲を刺激する
飲食店のYouTubeチャンネルを伸ばすためには、動画でユーザーの食欲を刺激することが大切です。
視聴者の食欲を刺激することができれば、お店に足を運んでくれる可能性が高まります。
また、他のSNSのシェアによる動画の拡散も期待できます。
そのため、飲食店の動画は、「いかに視覚的に美味そうにみせるか」が重要になります。
また、おいしそうに食べている方の様子をアピールするのも効果的です。
③お店の情報を明記する
お店の名前や住所、メニューの名前など、必要な情報を分かりやすく明記するようにしましょう。
動画内で伝えるだけでなく、概要欄にも文章で記載するとさらに効果的です。
動画を見て興味を持った視聴者が迷うことなくお店の情報を受け取れるように、しっかりと対策しておくことが重要です。
④自分自身のスキルを発信する
飲食店を構えるまで苦労してきた経験や、培ってきた料理スキルを動画で発信することも一つの手段です。
出演者の経験やスキルを有益だと感じた視聴者は、自然とチャンネル登録をしてくれるはずです。
飲食店経営の苦労話やノウハウを発信することで、将来的に飲食店を開業したい人もファンとして取り込めるでしょう。
また、「出演者のもとで働きたい」「料理・経営スキルを学びたい」という人も取り込むことができ、採用につながる可能性もあります。
お店やメニューの紹介、店内の雰囲気を公開するだけでなく、自分自身の経験やスキルもYouTubeで発信することが重要です。
⑤伸びる仕組みを理解する
YouTubeには検索したときに上位表示させるための施策がいくつか存在します。ただやってみたいことを動画に撮ってあげていくだけでは、いつまで経っても登録者は増えず、かかった費用は無駄になってしまいます。
そのため、ある程度事前にどういった方向性で進めていくのか計画し、どんな動画が伸びるのかのリサーチが非常に重要です。
仕組みを理解し施策を実施することで、多くの人に飲食店を知ってもらいましょう。
YouTubeのSEO対策方法についてはこちらの記事を参考にしてみてください!

⑥YouTubeショート動画を作成する
YouTubeショート動画とは、YouTube上で60秒以内の短い動画を投稿できるサービスです。
従来のYouTube動画と異なり、縦型の動画をフルスクリーンで表示させることが可能です。
視聴者はスクロールによって別の動画を視聴することが可能なため、スムーズに別の動画を視聴することができます。
気軽に視聴できる分、多くの視聴者にアプローチすることができ従来の動画よりも伸びやすいため、ショート動画により新規の視聴者を獲得することができます。
YouTubeショートについてはこちらの記事を参考にしてみてください!

飲食店がYouTubeで取り入れている動画の事例
。飲食店がYouTubeを取り入れる場合、ターゲットを明確にして最適な情報を含んだ投稿を心がけることが重要です。ここからは、飲食店がYouTubeでどのような動画を投稿しているのか、具体例を交えて解説してきますので、参考にしてください
レシピ紹介

出典:@ChefRopia
レシピ紹介は、飲食店がYouTubeで投稿する動画のなかで最もメジャーな動画です。
飲食店がYouTubeでレシピ動画を配信すると聞くと、家でお店の味を楽しめるようになってしまい、来店してもらえなくなるのではないか。と考えられがちですが、そんなことはありません。
例えば、Ristorante Floriaのオーナーシェフである、小林氏が運営する「Chef Ropia料理人の世界」では自店の人気メニューを実際に厨房で料理するかたちでご紹介しています。難しい工程を簡略化して視聴者が真似できるようにすることがポイントです。
アレンジレシピが評判になれば、次はお店の味に期待が膨らむでしょう。
また、使用する食材や道具をYouTubeをとおして販売する仕組みを作れば、売上のさらなる拡大が図れるでしょう。
食レポ

出典:@SUSURUTV
食レポをシェフやスタッフが行うことで、視聴者は店舗をより身近に感じられるようになります。
具体的には、どのような料理が食べられるのかはもちろん、店内やスタッフの雰囲気が分かることで、来店のハードルを下げることができるでしょう。
また、コラボ形式でほかのYouTuberに食レポをしてもらえば、店舗の認知度を一気に上げられる可能性があります。
例えば、「SUSURU TV.」ではさまざまなラーメン店をリアルな反応とともに紹介することで、視聴者の食欲を刺激しています。
食レポでの臨場感を出すためには、食感や香りを詳しく表現し、シズル感のある映像を意識することがポイントです。
アレンジメニュー紹介

既存のメニューをアレンジして意外性を引き出すことで、顧客の注意を一気に惹きつけることが可能です。
例えば、「丸亀製麺」では、うどんの新しい食べ方としてポテトのように揚げるといった、自宅で試せる面白いアレンジメニュー動画を投稿しています。
アレンジメニュー紹介をすることで、認知度を高められ、顧客接点の拡大やファンの創造につなげられるでしょう。
さらに、アレンジメニューを消費者から募り、店舗限定メニューとして提供すれば、話題性を生み、さらなる来店促進も期待できます。
ショートドラマ

ショートドラマとは、料理や店舗の魅力をストーリー仕立てで伝える動画です。
例えば、「マクドナルド」では、店員とお客様との心温まるエピソードを短編ドラマとして表現しています。店舗の親しみやすさを伝えるのに有効な技法といえるでしょう。
また、飲食店であれば、メニューの開発秘話や厨房の裏側、飲食店あるあるなどをドラマ仕立てで描くことで、お客様の共感を得やすくなります。
短時間で視聴できる内容にすることで、店のこだわりや世界観を自然に伝えられるのが、ショートドラマの魅力です。
飲食店のYouTube成功事例

では実際、飲食店はどのようにYouTubeを用いて集客を行っているのでしょうか。
ここでは実際にYouTubeを活用している飲食店を二つ紹介します。
くら寿司

大手回転寿司チェーン店「くら寿司」は、楽しく、明るく、くら寿司を紹介するというコンセプトのYouTubeチャンネルを運営しています。
2019年からチャンネルを開設し、今では約600本ほどの動画が投稿されています。
YouTubeの動画では普段見かけるテレビCMの雰囲気と異なり、くら寿司の社員がYouTuberとして顔出しして配信しています。
くら寿司の紹介だけでなく、実際に働く人へのインタビューやメニューのおすすめ、独自の企画など様々な動画を投稿しています。
また、最近ではショート動画にも力を入れていて、トレンドを意識した動画が投稿されています。
編集を含む動画の盛り上げ方や登場する人物のユーザーへの伝え方など、参考にできるポイントがたくさんあります。
ケーキ屋 ビルソンローラーズ

東京・豊島の椎名町にあるケーキ屋「bilsonrollers」は、10年前からYouTubeを活用しています。
最初は社員教育用動画を業務効率をあげる目的で投稿していました。
しかし、一部を一般公開したところチャンネル登録者数が3000人になっていたそうです。
ケーキ販売は利益率が高くないため、店舗以外で利益を上げる方法を考えていたところ広告収益に目を付け
本格的に取り組もうと考えたそうです。
YouTubeの動画を見た人が店舗に行かなくてもケーキを購入できるように通販での販売も行っています。
編集をあまり入れずにリアルタイムに近く、解説が細かいことが特徴です。
パティシエのスキルアップのために視聴することもでき、自身の飲食店開業後に動画で紹介したレシピを活用していいそうです。
焼鳥どんの飲食店あるあるチャンネル

焼鳥どんの飲食店あるあるチャンネルは、登録者数37万2,000人を誇り、累計再生回数は10億回をこえる人気YouTubeチャンネルです。
運営するのは都内で焼き鳥店を3店舗運営するオーナーの日垣さん。唯一無二のユニークなキャラはTikToKでもバズっており、27万人超えのフォロワーを持つインフルエンサーです。
とくに、飲食店で働いたことのある方なら思わず頷いてしまうシチュエーションをユーモラスに描いたショート動画が人気を集めています。
一方で通常の投稿投稿では煮込み料理の作り方やレモンサワーの作り方などのレシピ動画を発信しているのが特徴です。
ショート動画で注意を惹き、通常の動画で料理をメインとした動画を見せることで、SNS上でのファンを作りながら店舗への来店も促すような戦略が見て取れます。
人気の秘訣は飲食店経験者ならではの実体験に基づいた、リアルで共感生の高いコンテンツ配信にあると考えられるでしょう。
また、オーナー自身の個性的なキャラクターやベンチプレス220kgを挙げるという人並外れたパワーの持ち主といった意外性も、チャンネルの魅力です。
ぼなぺTV Bonapetv

登録者数12.7万人、最大再生回数93万回を誇る「ぼなぺTV Bonapetv」は、日本人オーナーシェフ・TOSHIがイタリアで営むイタリア料理店を紹介しているYouTubeチャンネルです。
レシピ本も出版しており、現在Amazon売れ筋ランキング1位を獲得しています。
チャンネルでは、定番のペペロンチーノやトマトパスタ、ナスを使ったアレンジ料理など、パスタを中心に多彩なレシピを紹介。
視聴者が真似しやすい内容が好評で、TOSHIと「ぼなぺTV」の掛け合いや、お茶目なイタリア人の登場も魅力の一つです。
また、YouTubeの強みを活かし、世界中の視聴者をターゲットにできるため、日本国内の飲食店も海外からの顧客獲得につなげられる可能性があります。
イタリア旅行のついでに店舗を訪れる日本人も多く、本場の味を気軽に学べるチャンネルとして人気を集めています。
小倉知巳のイタリアンプロ養成講座

小倉知巳のイタリアンプロ養成講座は、東京・代々木のミシュラン一つ星レストラン「Regalo(レガーロ)」のオーナーシェフ・小倉知巳氏が運営するYouTubeチャンネルです。登録者数は21.9万人、最大再生回数は306万回を記録しています。
ミシュラン一つ星ながら、親しみやすいレシピや料理をワンランク上げるポイントを紹介。レシピだけでなく、新メニュー開発の裏側も公開し、店のこだわりが伝わる内容となっています。
また、メンバーシップ制度を導入し、料理技術だけでなく、一流シェフの考えを学べる点も魅力。料理人からも高い評価を得ています。
動画は分かりやすく、再現しやすいのが特徴で、自分で作って美味しさを実感すれば、実際にシェフの料理を味わいたくなることでしょう。
無駄なし!まかない道場(MAKANAI DOUJYOU)

「無駄なし!まかない道場(MAKANAI DOUJOU)」は、小田原の居酒屋「まねき屋」の店主が運営するYouTubeチャンネルです。料理人歴40年以上の経験を活かし、簡単で美味しい料理の作り方を紹介しています。
チャンネル登録者数は約34万人、投稿動画数は2,600本以上。貝類のさばき方や刺身、焼き物、鍋料理など、多彩なレシピを発信し、特に居酒屋のまかない料理をまとめた動画が人気です。
2023年12月のまかない料理を一挙公開した動画も話題となりました。
また、チャンネルの人気を受けて、居酒屋の味を手早く再現できるレシピ本「パパッと極旨!おつまみ道場」も出版。プロの技術を家庭で楽しめる工夫が、多くの視聴者から支持を集めています。
自社運用が難しい場合は運用代行に相談を
YouTubeをはじめようと検討している方の悩みといえば、ノウハウやリソースの不足ではないでしょうか。
上記で紹介した成功事例はほんの一握りで、必ず同じように成功できるとは限りません。
YouTubeをはじめとするSNS運用を成功させるには、お客様の購買行動やニーズを深く理解し、それらに即したコンテンツ展開が必須です。
また、定期的な更新が必要となり、ネタ探しで燃え尽きてしまうケースも少なくありません。
しかし、運用代行を利用することで、これらの悩みは一気に解決することができます。運用代行を利用するメリットは以下のとおりです。
- SNSのプロに任せられる
- SNSやマーケティングの知識は不要
- ノウハウやリソースがなくても投稿を開始できる
- 効果的なYouTubeの投稿が可能
また、YouTubeのみならず、TikTokやInstagramなどのさまざまなSNS運用を同時に行うことで、多角的なアプローチが可能となります。
認知拡大から来店促進、顧客のファン化まで、一貫して行えるSNSは現代には必須のツールといえるでしょう。
まとめ
本記事では、飲食店を経営している人が集客を目的としてYouTubeを始めるメリットやコツについて成功事例を交えて解説しました。
YouTubeを用いて集客することで、飲食店の売上を上げるだけでなく、広告収益を得られたりファンを増やしたりすることができます。
しかし、YouTubeで結果を出すためには継続して動画を投稿することが重要です。
自社で継続することが珍しい場合、運用代行を用いるのも一つの手段です。
SNS運用はコンテンツを増やしていくことが重要。少しでも悩んでいるなら、その時間はもったいないといえます。少しでも興味があれば、まずはお気軽にご相談からどうぞ!
※株式会社シュビヒロでは、企業様のYouTubeを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたらフォームよりお問合せください。
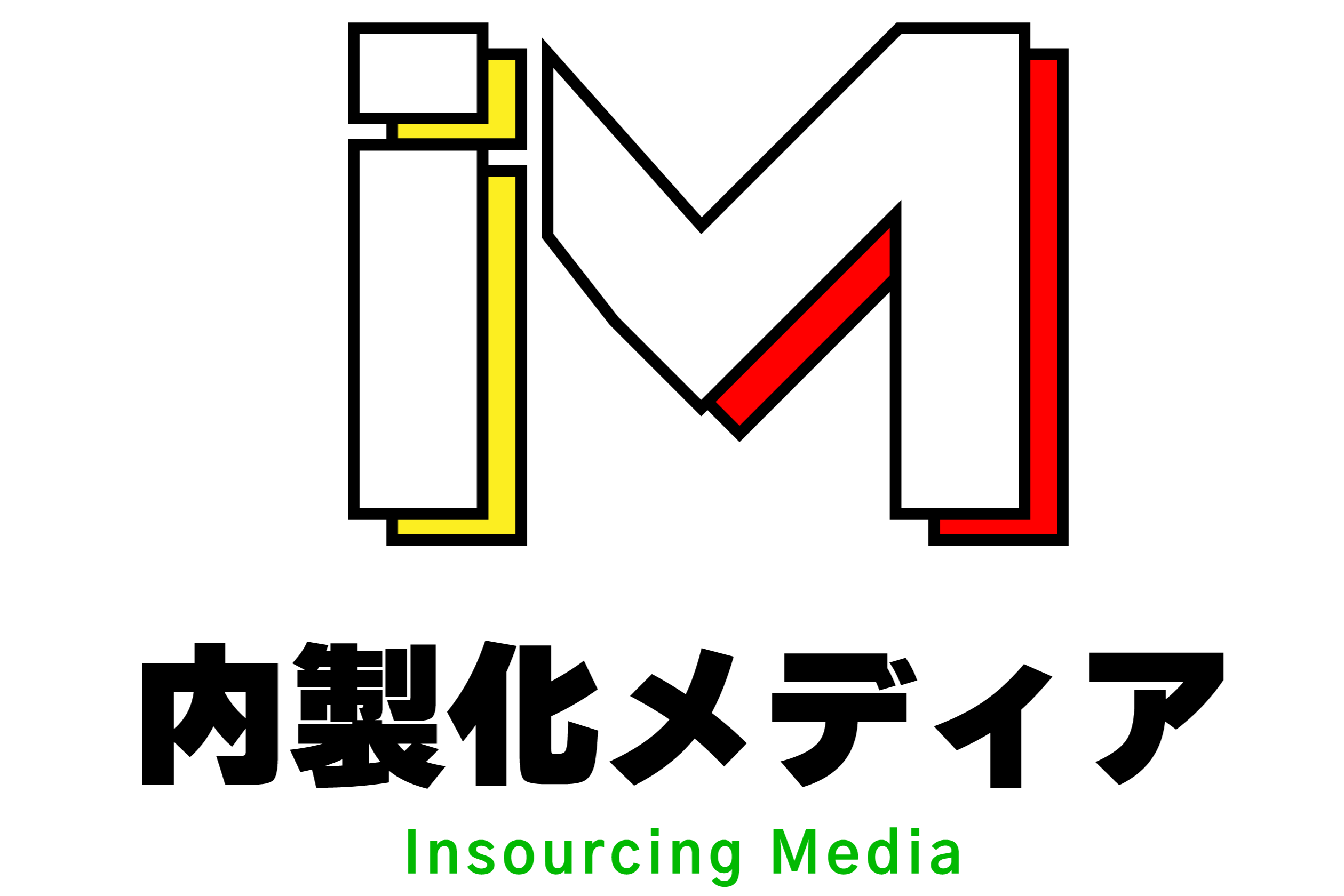


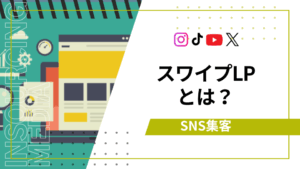




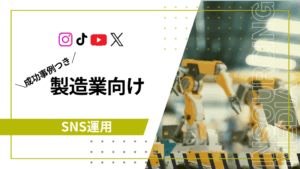
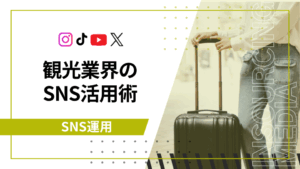

コメント