行政書士のSNSは戦略が命!運用のコツや成功事例を解説
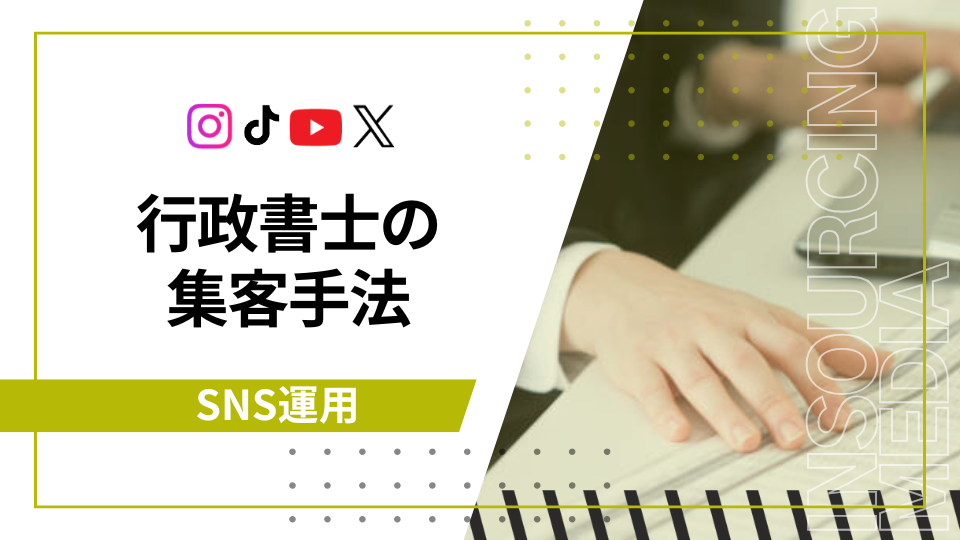
SNSを活用した集客は、いまや行政書士にとっても欠かせない戦略のひとつです。専門性の高い業務こそ、わかりやすく発信すれば「この人に相談したい」と思ってもらえる武器になります。
本記事では、行政書士がSNSで集客するべき理由から、実際に成果を出すための戦略、さらには成功事例までを網羅的に解説。さらに、自社では運用が難しい場合の代替手段として、SNS運用代行の活用方法にも触れています。
SNSとホームページを両軸で活かし、継続的な集客につなげたい方は、ぜひ参考にしてください。
SNSの集客方法に関して、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
⇒SNS集客の成功法則!5つの秘訣とSNS別アルゴリズムを徹底解説
※株式会社シュビヒロでは、幅広くSNSの運用代行が可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください
行政書士がSNSで集客するべき理由
行政書士として集客を考えるうえで、SNSは非常に有効な手段のひとつです。専門性の高いサービスだからこそ、信頼性や人柄が伝わる発信が求められます。
まずは、行政書士がSNSで集客するべき理由についてみていきましょう。
顧客との信頼関係を築きやすい
行政書士がSNSを活用することは、顧客との信頼関係を築くうえで有効な手段です。継続した情報発信は、活動状況の把握にもつながり、安心感や誠実な印象を与えられます。
また専門性が高い行政書士の場合、要点を絞って丁寧に伝えることが重要です。噛み砕いたわかりやすい情報によって、「相談しても大丈夫」と思ってもらえる可能性が高まります。
内容の質だけでなく、継続的に発信を続けることで、顧客の信頼を獲得できるでしょう。
無料で始められ、継続的な発信で資産になる
SNSの最大のメリットは無料で始められる点です。アカウント作成に費用がかからず、広告と違って予算を気にせず情報発信ができます。
初期コストを抑えながら集客活動をスタートできるため、開業間もない行政書士にとっては取り入れやすい手法といえるでしょう。
さらに、日々の投稿は自社の資産になっていきます。実際、過去の投稿が検索やSNS内で再び閲覧されることで、新たなフォロワーとの接点が生まれるケースも少なくありません。こうした見返される質の高いコンテンツを意識して継続的に発信することで、情報が蓄積され、中長期的な集客効果を発揮します。
幅広いターゲットへのリーチが可能
SNS利用率は年々増加しており、総務省「令和6年通信利用動向調査」によれば、全世代の81.9%に達しており、10代から60代以上まで幅広く普及しています。
つまりSNSは、行政書士の許認可手続や助成金・補助金などの経営者向けの情報発信だけでなく、遺言書の作成や遺産相続といった個人向けの情報を届けるための重要なチャネルということです。
ハッシュタグをうまく活用すれば特定の地域や業種、ジャンルのターゲットに投稿を効果的に届けることができます。最新の助成金の申請期限や要件変更、許認可申請の成功事例などリアルなニーズに直結したコンテンツを定期的に発信することで、経営者の関心を惹きつけることも可能です。
幅広い年代に届くSNSだからこそ、戦略的に活用することで、行政書士としての専門性を高められます。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
行政書士におすすめのSNS4選
SNSにはそれぞれ特性があり、行政書士として効果的に活用するには媒体ごとの特徴を押さえることが重要です。発信内容やターゲット層に応じて使い分けることで、集客や信頼構築のスピードが大きく変わってきます。
ここからは、行政書士にとって特に相性の良いSNSを4つ厳選し、それぞれの活用ポイントや事例を紹介します。どのSNSを選ぶか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
X(旧Twitter)
リアルタイム性に優れたX(旧Twitter)は、法改正や補助金などの最新情報をタイムリーに届けるのに適しています。140字という文字数制限のある短文投稿は、要点を簡潔に伝えるのに効果的です。
社会動向やニュースに対する専門家の見解を発信することで、信頼性の高い情報源として認知されやすくなります。
TikTok
TikTokは15〜60秒のショート動画が中心のSNSで、専門的な内容も図解やナレーションを交えることで視覚的にわかりやすく伝えられるのが特徴です。
たとえば「補助金申請に必要な3つの条件」や「相続手続きの流れ」といったテーマも、アニメーションや字幕を活用してテンポよく解説すれば、短時間でもユーザーの理解を深められます。
専門性と親しみやすさを両立できるため、認知拡大や顧客獲得のきっかけづくりに効果的なプラットフォームです。
YouTube
YouTubeは長尺コンテンツに強く、行政手続きや起業支援などを体系的に丁寧に解説する動画に適したプラットフォームです。話し方や表情を通じて人柄が伝わるため、視聴者に安心感を与え、信頼構築にもつながります。
また、動画を通じてサービス内容を深く理解してもらえるため、成約率の向上にも効果的です。ただし、撮影や編集に一定の時間と手間がかかるため、継続的な運用には計画的な準備とリソース確保が欠かせません。
LINE
LINE公式アカウントは、ユーザーと1対1で接点を持てるツールとして活用されています。セミナー情報や手続きの案内、個別相談の誘導など、タイムリーでクローズドな情報提供が可能です。
また、配信は一斉にも個別にも行えるため、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。継続的な接触を通じて関係性を深め、相談や契約へとつなげられます。
行政書士が成果を出すためのSNS戦略と成功ポイント
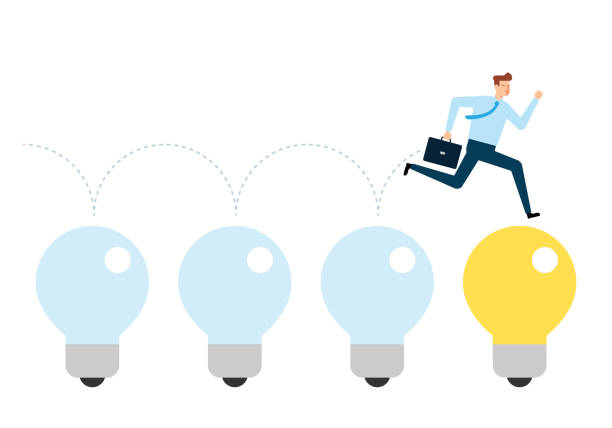
SNSをただ運用するだけでは成果にはつながりません。ここからは、成果につなげるための具体的なSNS活用のポイントと、実際に意識すべき運用ノウハウを紹介します。
専門性を活かした情報発信で信頼を得る
SNSで信頼を築くには、自身の専門知識を活かした継続的な発信が欠かせません。たとえば補助金申請や建設業許可、在留資格手続きなど、行政書士が扱う分野について、実務事例や最新動向をわかりやすく伝えることが効果的です。
難解なテーマをかみ砕いて解説すれば、専門性と同時に親しみやすさも伝えられます。また実績紹介や対応事例の共有も、信頼獲得の後押しになります。
さらに、投稿から自社サイトやブログへの導線を設けておけば、関心を持ったユーザーが詳細を確認しやすくなり、問い合わせや申し込みの増加も期待できるでしょう。
顧客導線を設計し、申し込みへつなげる
SNSで集客成果を上げるには、ユーザーの行動を具体的に想定した導線設計が不可欠です。投稿を見て関心を持った人が、次にどこへアクセスして何をすべきかを明確に示しましょう。
たとえば、プロフィール欄や投稿内に公式サイトや問い合わせページへのリンクを記載しておくと、情報を深掘りしたいユーザーをスムーズに誘導できます。
Instagramではストーリーやリンク付きの投稿、Twitterではツイート末尾のURL誘導が有効です。さらに、相談事例や感想など共感を得られるコンテンツを活用すれば、クリック率も高まるでしょう。
広告運用は費用対効果を見て柔軟に判断する
SNS広告を活用する際には、費用対効果を重視して冷静に判断することが重要です。
SNS広告運用では、以下の3つの課金形式が利用されます。
- インプレッション課金(CPM):広告が1,000回表示されるごとに料金が発生。認知拡大を目的とする場合に最適。
- クリック課金(CPC):広告がクリックされるごとに料金が発生。リンク誘導やサイト流入を重視する際に有効。
- エンゲージメント課金(CPE):「いいね」「シェア」「コメント」などのアクションごとに料金が発生。投稿への反応を促したい場合に向いている。
広告の投資効率は「売上 ÷ 広告費 ×100(%)」で計算されるROASによって確認できます。たとえば売上500万円に対して広告費が100万円ならROASは500%となる計算です。この数値が高いほど効果的とされ、施策ごとの優先順位を見極める指標になります。一方で、ROASが100%を下回っている場合は、売上よりも広告費の方がかかっていることとなり、いわゆる赤字状態を意味します。
戦略的な広告運用でターゲットにアプローチする
SNS広告を活用するうえで重要なのは、やみくもに配信するのではなく戦略的に設計・運用することです。以下のような流れで広告運用を進めることで、狙ったターゲットに効率よくリーチできます。
- ターゲットと目的を明確に設定
- 少額予算でテスト広告を配信
- 結果を分析し、効果の高いパターンを絞り込み
- 改善と再配信を繰り返して最適化
まず、広告運用では「誰に」「何を」「どう届けたいか」を明確にすることが最優先です。たとえば、ビザ申請サポートを行う行政書士であれば、外国人労働者を多く抱える企業の人事担当者などを想定してターゲットを設計します。
次に、いきなり高額な広告費を投入するのではなく、少額でテスト配信を行いましょう。複数パターンの広告を出し、それぞれの反応を比較することで、どの訴求が効果的かを見極めることが可能です。
その後は、効果が高かったパターンを軸に広告内容を最適化し、本格的な配信を行います。さらに配信後もクリック率やコンバージョン率をもとに随時PDCAをまわしていき効果の最大化を目指していきましょう。
このように、広告運用は一度きりで完結するものではなく、設計から効果測定、改善までを繰り返すプロセスが重要です。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
SNSごとに役割を持たせ、マルチチャネルで発信する
SNSを効果的に活用するには、各媒体の強み活かした役割を持たせる工夫が必要です。
それぞれのSNSと活用方法を以下にまとめました。
| ・視覚的に印象を残すブランディングに最適 ・短文+画像やリールで認知を広げやすい ・雰囲気や人柄を伝える投稿に向いている | |
| X(旧Twitter) | ・法改正や補助金などの速報情報を発信しやすい ・専門性や考え方を端的に伝えられる ・リアルタイムな交流で認知・信頼を獲得 |
| YouTube | ・行政手続きや制度解説をじっくり伝えられる ・長尺動画で人柄や専門性を深く伝えるのに最適 ・検索流入にも強く、継続的な集客が可能 |
| ・既存の顧客や地域の関係者との接点づくりに有効 ・長文投稿やイベント案内など、詳細な情報発信に強み ・信頼維持・地域密着のコミュニケーションに活用可能 |
こうしたチャネルを戦略的に活用することで、多様な層にリーチしながら発信の幅を広げられます。媒体ごとの特性を活かして連携させることで相乗効果が生まれ、より強い認知と集客につながっていきます。
企業のSNSに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
企業SNS運用の完全ガイド!成果を出すSNS運用手順と失敗しない体制作り
自社に応用できる行政書士のSNS成功事例3選
ここからは、行政署にのSNS成功事例についてご紹介していきます。これらの成功事例をもとにして戦略を立てていくことで、より確度の高いSNS運用が可能になるでしょう。
YouTubeの成功事例:あやなみ行政書士事務所
出典:@ayanamiceo
横浜市の宮城彩奈氏(あやなみ行政書士事務所)は、士業としては早期からYouTube発信に取り組んできました。
動画では、行政書士の1日や試験勉強、開業後の苦労など、リアルな日常を等身大で発信しているのが特徴です。専門知識の解説のみならず「人となり」や「士業の現実」に焦点を当てることで、視聴者の共感を得ている好事例です。
宮城氏も「動画で専門性をアピールできるため、名前や声を先に知ってもらえることで初対面時の信頼が高まる」と語っており、事務所の認知拡大に成功しています。
TikTokの成功事例:ゆうせい行政書士
出典:yusei.gyosei
ゆうせい行政書士【ノーサイド行政書士法人/熊本】は、TikTokで補助金申請や相続手続き、建設業許可の情報をショート動画で発信しています。
専門性の高い内容を分かりやすく解説しているのが特徴です。補助金や相続といったニッチな分野でも、ユーザーの関心にマッチしたコンテンツとして高い評価を得ており、TikTokを通じて問い合わせが増えています。
X(旧:Twitter)の成功事例:みうらさとし
茨城県の社会保険労務士・行政書士であるみうらさとし氏は、X上で自身の学びや業務にまつわる雑談風投稿、法改正の解説などを発信しています。
日常的なつぶやきや経営観察を通じてフォロワーとの距離を縮め、専門家としてのブランディングを確立しているのが強みです。専門分野以外の発信も交えることで、ファンを獲得し、信頼につながっている好事例といえるでしょう。
行政書士の集客にはSNS×ホームページが効果的!
SNSを通じて行政書士に興味を持ったユーザーを実際の依頼へつなげるには、ホームページの存在が重要です。事務所のプロフィールや対応分野、料金、実績などを丁寧に掲載すれば、信頼性を高める情報源として機能します。
SNSでは伝えきれない細かな内容をホームページで補うことで、ユーザーの不安を取り除き、問い合わせへとスムーズに導くことが可能です。また、検索エンジン経由で訪れる新規ユーザーとの接点を確保できるのも大きなメリットです。
SNSとホームページを連携させ、相互にリンクを設けておけば、認知から相談・申込みまでの動線が自然につながります。両者を使い分けながら発信を続けることで、集客の安定性と質が大きく向上していきます。
- SNSは「認知獲得、興味喚起」、ホームページは「信頼の獲得、行動喚起」として役割分担
- ホームページでサービス内容・実績・FAQを明示し、問い合わせの不安を払拭
- 定期的なブログやコラム更新によりSEO効果・検索流入も獲得可能
- SNSと相互リンクを設けて、双方向の導線を確保する
行政書士がSNSを運用する際の注意点
行政書士がSNS運用する際には、いくつかの注意点があります。とくに信頼が求められる行政書士は、その投稿内容のチェックが重要です。
投稿やコメントの炎上リスク
SNSは情報が瞬時に広まりやすく、行政書士としての発言が炎上につながるリスクも少なくありません。法律や制度に関する発信は特に誤解を招きやすいため、投稿前には事実確認や表現のトーンを含めたセルフチェックが不可欠です。
さらに、投稿後のコメント欄にも注意が必要です。誤解を生む質問や挑発的なコメントが寄せられた際、放置や感情的な返信は信頼低下につながります。
丁寧で誠実な対応を心がけ、必要に応じて削除や非表示の判断も検討しましょう。SNSは発信力と同時に責任も伴うため、発信前後の管理を徹底することが信用維持のカギです。
守秘義務・個人情報の取り扱いに注意
行政書士は職業倫理として守秘義務を負っており、SNSでの発信にも十分な配慮が求められます。依頼者の名前や案件の詳細を明かすことはもちろん避けるべきですが、それ以外にも特定につながる情報を不用意に発信してはいけません。
とくに出身校や地域、職業など、本人が推測されるような情報の扱いには注意が必要です。さらに、SNS上の投稿は一度発信すると完全に消去することが難しく、非公開設定でもスクリーンショットや転載により拡散される恐れがあります。
発信前にはこの情報が公開されたままでも問題ないかという視点で見直すことが、信頼される専門家としての基本姿勢になります。
投稿の継続が途切れると逆効果
行政書士のSNS運用において、更新が数か月以上途切れていると、見込み客からは運営されていないと受け取られます。
さらに、長期間放置されたアカウントは、なりすましや不正アクセスのリスクにさらされることも注意です。仮に悪意ある第三者に乗っ取られてしまうと、虚偽の情報を投稿されたり、スパムや詐欺に利用されたりする恐れがあります。その結果、知らないうちに評判が下がることになるでしょう。
行政書士のSNS運用では、たとえ投稿頻度が少なくても、無理のないペースで情報を発信し、定期的に管理しましょう。継続した発信は、長期的な集客成果にもつながります。
業界ルールやガイドラインの遵守が必要
行政書士がSNSで情報を発信する際は、業界独自の規制をしっかり理解し、法令やガイドラインに沿った運用が求められます。
行政書士法や職務基本規則では、誤解を招く表現や過度な宣伝行為が禁じられており、SNSも例外ではありません。行政書士として活動する場合、投稿前のセルフチェックが欠かせません。守秘義務や広告規制への理解を深め、信頼を損なわない発信を心がけましょう。
行政書士が、守るべき主なルールは以下の通りです。
- 事実と異なる誇大広告の禁止:「必ず補助金がもらえる」「100%成功します」などの表現は禁止対象。
- 不当な誘引の禁止:過剰な割引や特典を餌にする依頼勧誘は不適切。
- 秘密保持と守秘義務の厳守:顧客情報や相談内容を不用意に公開することは法律違反。
- 誹謗中傷・ハラスメントの回避:他者を非難したり、攻撃的な発言を行うと信用と法的リスクの両面で不利益を被る。
SNS発信は自由度が高い一方で、発信者の責任も大きくなります。常に公共の場に公開する情報として慎重に扱いましょう。
全部やるのはハードルが高い!そんなときはSNS運用代行も視野に入れよう
SNS運用には専門的な知識と継続的な労力が求められます。業務の合間にすべてをこなすのは難しく、途中で更新が止まってしまうケースも少なくありません。
そうした場合は、運用代行サービスの活用もひとつの選択肢です。投稿内容の企画からスケジュール設計、広告出稿まで、プロの手で一貫して支援してもらえるため、成果を出しやすくなります。
シュビヒロでは、月額5万円から依頼できる低コストかつ高品質なSNS運用代行サービスを提供しています。Instagram、X(旧Twitter)、YouTube、LINEなど主要SNSの運用をはじめ、ホームページやLPの制作、広告運用、展示会ブースのデザインまで幅広く対応しており、複数のチャネルを掛け合わせた集客サポートも可能です。
- 初期費用・契約期間の縛りなし
- SNS運用+ホームページ連携による集客強化
- コンセプト設計からDM返信代行、投稿作成・分析までワンストップ対応
- 多業種100社以上の支援実績とノウハウあり
無理なく継続できる発信体制を整えたい方、発信の手間を減らしつつ成果を上げたい方は、ぜひ一度シュビヒロへご相談ください。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
まとめ:行政書士はSNS×ホームページの2軸が重要!
SNSで関心を集め、ホームページで信頼を深める。この二つの軸を連携させることで、行政書士の集客は着実に成果へとつながります。SNSでは人柄や専門性を伝え、ホームページでは実績やサービス詳細を丁寧に補足することで、依頼者の不安を解消し、相談のハードルを下げられます。
本記事では、行政書士がSNSを活用する理由から、媒体別の特徴、成功事例、そして運用時の注意点までを詳しく解説しました。
すべてを自分で抱えず、必要に応じて代行サービスを取り入れる柔軟さも、これからの集客には重要です。発信の質と継続力を意識し、信頼される事務所づくりを進めていきましょう。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
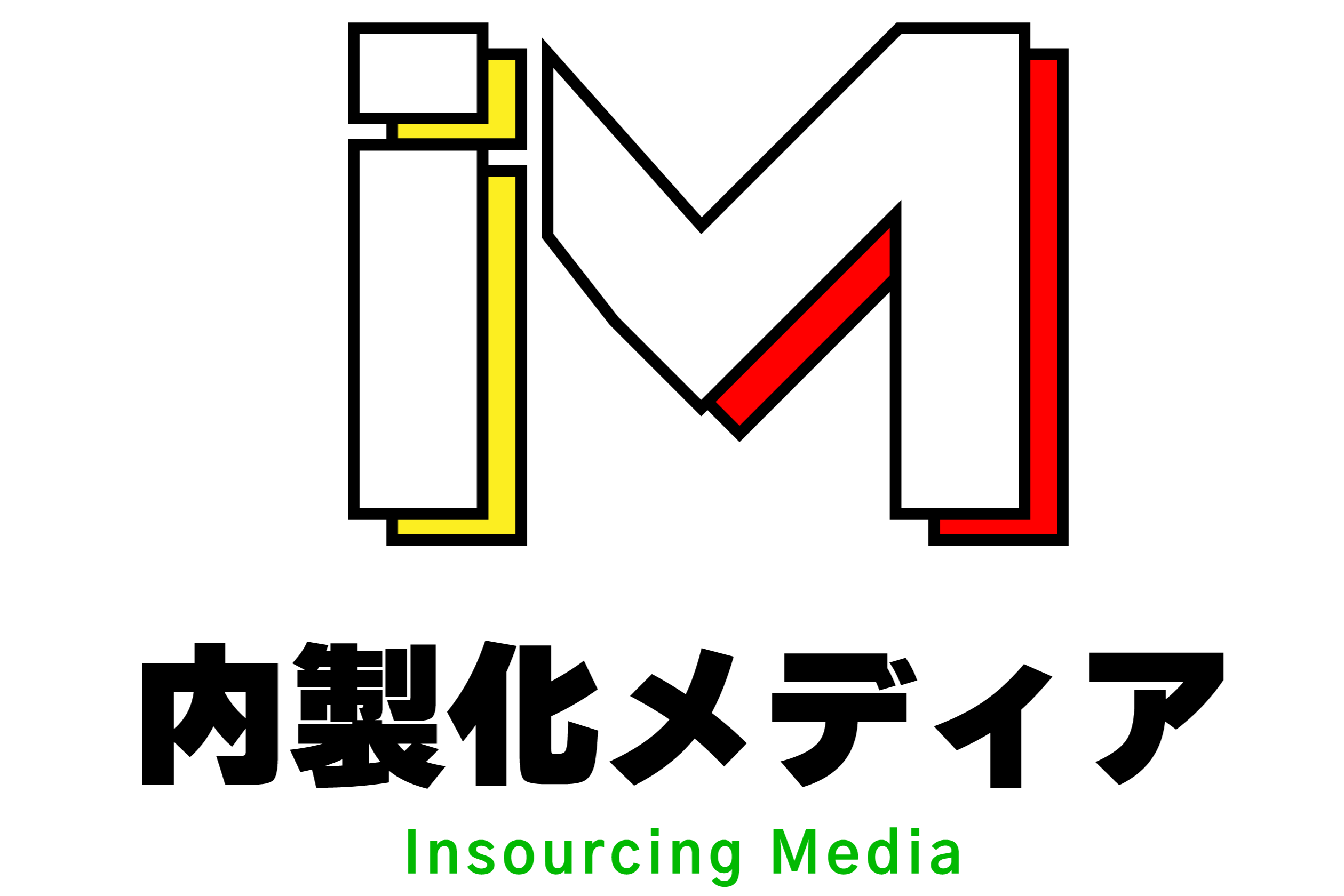
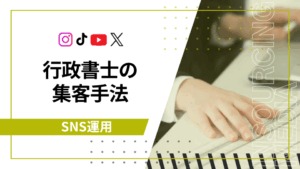



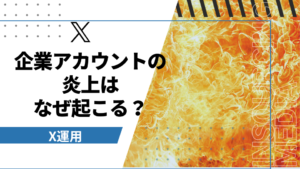
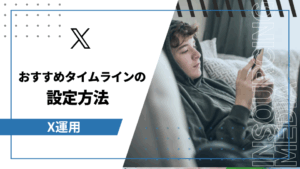

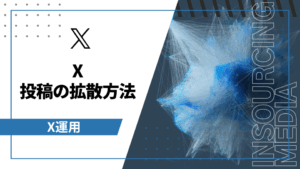
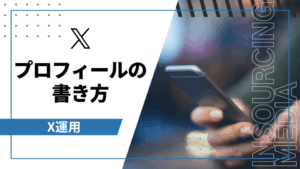
コメント