SNSマーケティングの成功事例9選!最新動向や戦略、コンテンツ制作まで徹底解説

SNSマーケティングは、いまや企業の認知拡大や売上向上に欠かせない施策です。しかし「どのSNSに注力すべきか」「成果を出している企業は何をしているのか」と迷う担当者も多いでしょう。
本記事では、最新のSNS動向を踏まえつつ、国内外の成功事例を9つ紹介します。さらにプラットフォームごとの特徴や目的別の運用ポイント、複数SNSを組み合わせた戦略まで徹底解説。明日からの運用に役立つ具体的なヒントが見つかります。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
SNSマーケティングの最新情勢と可能性

SNSは生活に密着した情報源となり、購買行動やブランド選好に強い影響を与える存在です。企業にとっても顧客接点を広げ、成果を生むマーケティング手段としての重要性がますます高まっています。
まずは、SNSマーケティングの最新情報と今後の可能性についてみていきましょう。
SNSマーケティングとは
SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)やInstagram、TikTok、YouTube、LINEといったソーシャルメディアを活用し、企業やブランドの認知拡大、顧客獲得、ファン育成を行うマーケティング手法全般のことをいいます。
大量のコストをかけ、不特定多数にリーチする従来の一方的な広告とは異なり、SNSではコメントやシェアを通じた双方向のやり取りが可能で、ユーザー参加型のプロモーションを展開できる点が特徴です。
また、SNSは検索や購買行動にも直結しており、単なる「広報チャネル」ではなく、売上やブランド戦略全体を支える役割を果たしています。こうした特性からいまや中小企業から大企業まで幅広い業種で欠かせないマーケティング施策といえるでしょう。
SNSマーケティングが注目される理由
SNSマーケティングが注目される主な理由は以下のとおりです。
- 国内SNS利用者は2027年までに約1億1,300万人となる予想
- 広告・運用コストは従来メディアに比べ低い
- コメントやDMで直接的な顧客接点を作れる
- シェアやリツイートにより短期間で拡散できる
SNSマーケティングは、消費者の生活に密接に関わり、短期間で大きな影響を生み出せる点から注目を集めています。とくに幅広い世代へのリーチやコスト効率の高さは、ほかのマーケティング手法にはない強みです。
こうした特徴から、中小企業から大企業まで幅広く取り入れられ、事業成長を支える重要な手段となっています。
SNSマーケティングの最新動向
SNSは日々進化しており、その変化に合わせてマーケティングの手法も常にアップデートが求められます。企業が成果を出すためには、この最新動向を理解し、柔軟に戦略へ取り込むことが不可欠です。近年SNSは、次のように変化しています。
- SNS投稿が検索流入を生む仕組みに変化
- SNS内での購買完結
- AIによるパーソナライズ化
- ナーチャリング施策の強化
2025年7月10日には、Instagramがプロアカウント投稿をGoogle検索に表示するアルゴリズムを導入しました。これは、SNSがSEO資産としての役割を担うようになり、より一層検索流入と結びついていることを意味します。
また、オンライン上で商品やサービスの認知から購入までが完結できる「Eコマース」の普及も注目です。調査機関の予測によれば、日本のEコマース市場は今後10年で大幅に拡大し、数千億ドル規模に達するといわれています。
さらに、DM配信やコミュニティ運営を通じて顧客一人ひとりとの関係を深める「ナーチャリング施策」も重要視されるようになりました。企業にとっては、これらの最新動向を戦略に組み込み、変化のスピードに追随できる体制を整えることが成果を左右します。
SNSマーケティングの成功事例9選

SNSマーケティングで成果を出している企業は、プラットフォームの特性を活かした工夫を行っています。ここではX(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTube、LINEといった主要SNSごとに、国内の成功事例を9つ紹介し、その目的や要因を解説します。
X(旧Twitter)の成功事例:①ライオン

ライオン(@TOP_superNANOX)は、NANOX one公式のX(旧Twitter)アカウントで、フォロワー数は15万人を超えています。「新人ナノ川のお洗濯プロへの道」をキャッチフレーズに、製品の使い方や魅力をユーザー目線で紹介しています。
投稿では柔らかなブランドトーンを用い、専門性だけでなく身近さを演出している点が特徴です。とくに、クイズやアンケートといった参加型の仕掛けを通じて双方向のコミュニケーションを促し、生活者の日常に寄り添うブランドイメージを強化しています。
結果として、一方的な広告発信ではなく「使ってみたい」「共感できる」と感じさせる運用が、SNS上でのブランド親和性と認知拡大につながっている事例といえるでしょう。
X(旧Twitter)の成功事例:②わかさ生活

わかさ生活は、健康食品メーカーが運営する公式X(旧Twitter)アカウントで、ブルーベリーキャラクター「ブルブルくん」を前面に出したユニークな発信が特徴です。日常風景にブルブルくんを登場させるユーモラスな投稿で親近感を醸成し、ファンとの距離を縮めています。
キャラクターを活かした独自性とトレンドへの柔軟な対応がこのアカウントの成功要因です。ブルブルくんと「中の人」のユーモアを融合させることで、視覚的にも言葉選びの面でも自然に拡散される投稿を生み出しています。
またトレンドワードを取り入れた機動力のある発信は、リアルタイム性が重視されるX(旧Twitter)に適しており、フォロワー17万人超を獲得する人気アカウントへと成長しています。単なる情報発信に留まらず、人間味を感じさせる双方向コミュニケーションが、ファン化とエンゲージメント向上につながった事例です。
Instagramの成功事例:①しまむら

ファッションセンターしまむらの公式Instagramアカウントは、フォロワー数が100万人を超えており、プチプラファッションとセール情報を中心に、ユーザーとの距離感が近い発信を続けています。視覚的に統一されたデザインと、しまパト呼ばれるハッシュタグを活かしたユーザー投稿のリポストが強みです。
しまむら公式Instagramは、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用が大きな成果を生んでいます。消費者が「#しまパト」で投稿した購入品やコーディネートをリポストすることで、リアルな声を拡散する好循環を作り出すことに成功。
投稿は正方形フォーマットで統一され、見やすさとブランドの世界観を両立させています。さらに、インフルエンサーとのコラボによって情報の広がりを強化し、フォロワー100万人超の人気アカウントへと成長しました。単なる広告発信ではなく、ユーザーと共にコミュニティを育てる運用が支持を集めています。
Instagramの成功事例:②令和の伊能忠敬
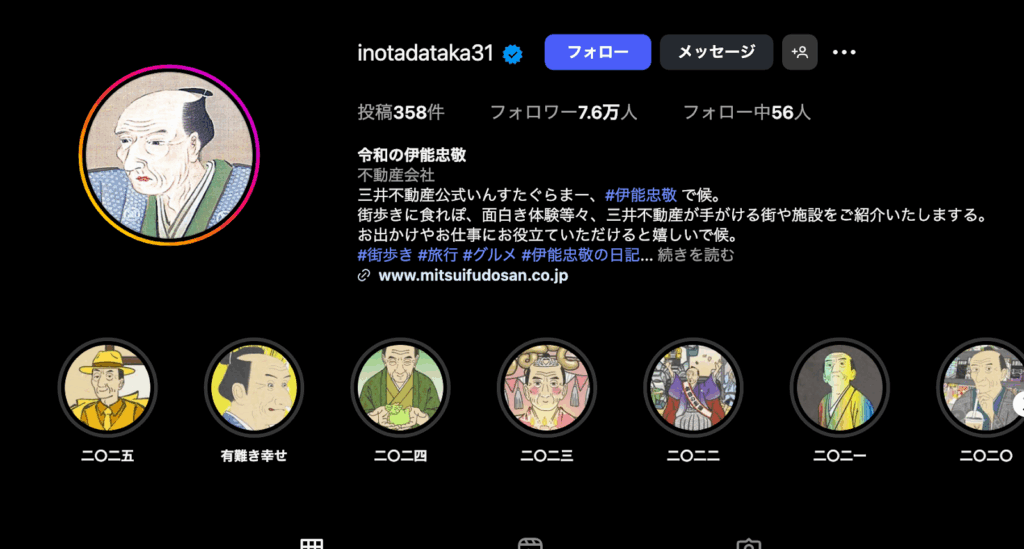
三井不動産が運営する令和の伊能忠敬のInstagramは、江戸時代の地理学者・伊能忠敬が現代を「浮世絵風」に紹介する斬新なキャラクター発信が魅力です。街歩きや施設をユーモラスに描写し、視覚的インパクトとブランド訴求を両立したアプローチで注目を集めています。
このアカウントの成功は、歴史的キャラクター「伊能忠敬」と、浮世絵風イラストという強いビジュアルアイデンティティが鍵です。古典と現代が融合した新感覚ネオ浮世絵という演出が目を引き、SNS上で自然と拡散・話題化されました。
また、投稿は「古文調テキスト」で統一されており、独自の世界観をブレずに発信。これにより差別化に成功し、ブランド認知の拡大とファンとの継続的な関係構築を実現しています。単なる施設紹介にとどまらず、見る人に新しい視点と楽しさを提供することで、発信が消費者体験として定着している点が運用の要といえるでしょう。
TikTokの成功事例:①ドミノピザ

ドミノ・ピザの公式TikTokは、メニュー紹介に加え「ピザあるある」や豆知識など、遊び心あるコンテンツで注目を集めています。調理工程や大量トッピングチャレンジといった動画はスタッフが出演し、テンポの良い編集やトレンド音源でエンタメ性を高めて飽きさせない演出が魅力です。
とくに注目されたのは、最高チーズ責任者(CCO)に選ばれると日給100万円が得られる「#ドミノチーズ100万」キャンペーンを開催したことです。このような大胆な取り組みは、ユーザー参加と拡散を一気に促進し、アカウントの成功に寄与しました。
またコメント欄ではユーザー同士の交流も活発で、単なる広告を超えてコミュニティを形成しているのも特徴です。ブランドとユーザーが共に楽しむ仕掛けが、人気アカウントとして支持される要因です。
TikTokの成功事例:②ドン・キホーテ

ドン・キホーテの公式TikTokアカウントは、ユニークで目を引く商品紹介動画を通じて幅広い注目を集めています。実際に1,000万回超の再生を記録した投稿も複数あり、短時間でインパクトを与えるコンテンツ設計が特徴です。
動画は20秒前後で商品の魅力を端的に伝え、視聴者の「試してみたい」という行動を促す編集は参考になります。さらに、従来のフォロワー数ではなく「再生回数」をKPIに据え、制作リソースの投資先を明確化したことが成果に直結しました。
また、コメント欄を活用して店頭POPのコピーを募集する「#みんなでドンキのPOPつくってみた」キャンペーンを展開し、SNSと実店舗をつなげた点も特徴です。こうした企画性と運用設計により、ドン・キホーテは単なるバズに留まらず、売上やブランド認知の拡大へと結びつける成功を収めています。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
YouTubeの成功事例:①永田 ハードオフ久留米国分店

「永田 ハードオフ久留米国分店」は、店長の永田氏が自身で企画、撮影、編集を担当するYouTubeチャンネルです。ジャンク品の楽器でX JAPANの「Rusty Nail」をカバーし再生数が100万回を超えるなど、店舗PRの枠を超えた注目を獲得しています。
永田 ハードオフ久留米国分店の成功の要は、「個人の熱量」を全面に出した発信スタイルにあります。ジャンクのギターや壊れたキーボードといった独創的な素材を使い、自ら演奏・歌唱・撮影・編集まで行った一点突破の企画が、他とは一線を画す魅力となりました。
さらに、話題性が話題を呼び、X JAPANのYOSHIKI氏からリツイートされるなど、メディア拡散にもつながった点も大きな要因です。店舗コンテンツが個人の力によってバズることで、集客・求人・ブランド認知といった幅広い効果をもたらした成功事例といえます。
LINEの成功事例:①@cosme

@cosmeのLINE公式アカウントは、日本最大級の化粧品・美容レビューサイト「@cosme」と連携し、信頼性の高い情報と限定クーポンの配信を行っています。コスメの最新情報や口コミランキングを紹介する仕組みを通じて、ユーザーの関心を日常的に惹きつけています。
特徴的なのは、LINE上で「キーワードを送信するとカテゴリー別のランキングを確認できる」というサービスです。ユーザーは気になったタイミングで手軽に活用でき、利用のハードルが低い点が強みとなっています。この仕組みによって、興味関心が高いユーザーを自社サイトに自然に誘導でき、購買意欲の高い層を効果的に獲得していると考えられるでしょう。
また、口コミとレビューに基づいた情報発信は、ブランドへの信頼感を醸成する重要な要素のひとつです。限定クーポン配信や双方向的なサービス機能と組み合わせることで、「友だち登録して得られる価値」が明確になり、結果的にロイヤリティの向上と売上促進を両立させている点が成功要因といえます。
LINEの成功事例:②さくらフォレスト株式会社
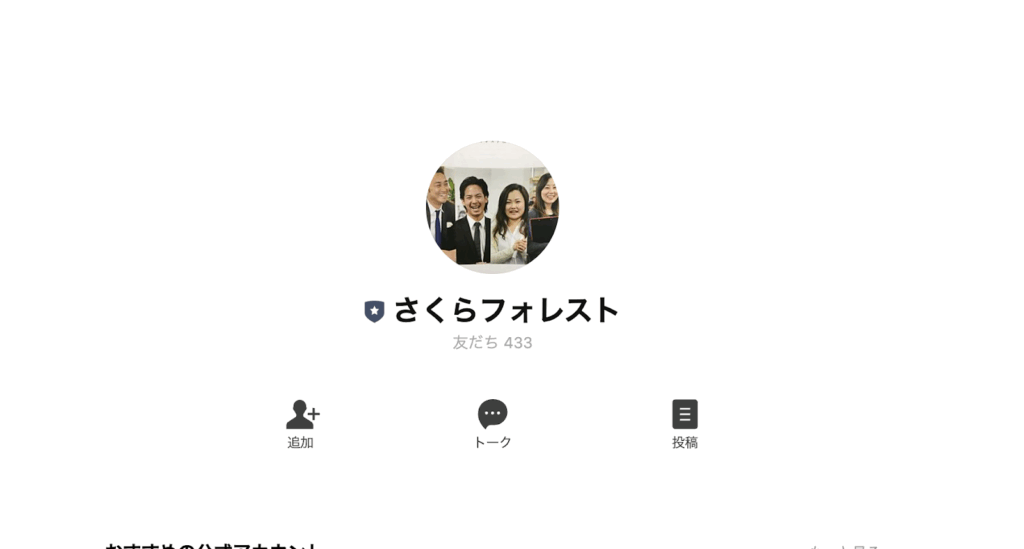
さくらフォレスト株式会社は、健康食品やスキンケア製品を自社通販で展開する企業です。ユーザーとの信頼関係を重視し、長期的に続けられる健康習慣を提案する一貫したブランド姿勢が特徴です。LINE公式アカウントやLINE広告を積極的に活用し、効率的な新規顧客獲得を推進しています。
成功事例として注目されるのはLINE広告の運用改善によってわずか3カ月で新規コンバージョン数を約6倍に拡大した点です。他媒体で成果が出ていたクリエイティブをLINE広告に展開することで視認性を向上させました。
さらに、類似オーディエンスを30種類以上作成し、ターゲティングを最適化したことで。コストを抑えつつ1日あたり200〜300件の新規獲得を安定して実現しています。短期間で高効率な成果を出したこの施策は、LINE広告の活用可能性を示す代表的な事例といえるでしょう。
代表的なSNSごとの特徴と最適なコンテンツ

SNSごとに利用者層や利用目的が異なるため、適切なコンテンツ設計が欠かせません。ここでは主要なSNSの特徴と、企業アカウントに最適なコンテンツの方向性を解説します。
Instagramは20〜30代を中心に利用されるビジュアル重視のSNSです。写真や動画を通じたライフスタイル提案や購買行動との親和性が高く、ブランドイメージの訴求に適しています。とくにリールやストーリーズなど短尺動画の普及により、拡散力と日常的な接触を両立できる点が強みです。
Instagram運用では、世界観を統一した写真や動画で商品やブランドストーリーを伝えることが重要です。ストーリーズでは日常的な発信やキャンペーン告知を行い、リールではトレンドに沿った短尺動画で拡散を狙うと効果的といえます。
さらに、ショッピング機能を活用して商品ページへ直接誘導すれば購買までスムーズにつなげることも可能です。UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用によって顧客の共感や参加を促すことも、ファンコミュニティの形成に大きく寄与します。
X (旧Twitter)
X(旧Twitter)はリアルタイム性と拡散力に優れ、10〜40代まで幅広い層が利用するSNSです。ニュースやトレンドとの親和性が高く、速報性のある情報発信やユーザーとの直接的な対話に適しています。短文投稿の特性を活かし、迅速かつフラットに企業の声を届けられる点が強みです。
企業がX(旧Twitter)を効果的に活用するには、新製品発表やキャンペーン告知といったタイムリーな情報発信が欠かせません。トレンドハッシュタグを組み合わせれば、フォロワー以外へのリーチを拡大できます。さらにリプライや引用投稿でユーザーと交流し、双方向性を演出することが重要です。
BtoB企業であれば業界ニュースや専門知識の発信による信頼構築が有効であり、採用活動では社風や日常の雰囲気を短文で伝える活用法もあります。継続的な発信を重ねることで、企業の透明性と信頼感を高められるSNSです。
Facebookは30〜50代を中心に利用が多く、とくに管理職層やBtoB領域のユーザーに強いプラットフォームです。ニュースや長文投稿に適しており、コミュニティ形成やイベント集客、さらに高精度な広告ターゲティングが大きな特徴となります。
運用では「情報の蓄積と共有」を意識すると効果的です。BtoB企業は業界レポートや展示会告知、BtoC企業は新商品やキャンペーン情報の発信が相性の良いコンテンツです。
また、イベント機能を使ってウェビナーやリアルイベントへの参加を促せるほか、広告では年齢・職業・関心に基づく詳細なターゲティングが可能です。さらに、コメントやグループを活用して双方向性を持たせることで、ブランドへの信頼感を高められます。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
TikTok
TikTokは10〜20代を中心に支持されるショート動画特化型SNS。トレンドや音楽との相性が良く、拡散力に優れているのが特徴です。投稿はフォロワー以外にも届きやすく、最新の動画だけでなく過去のコンテンツも再表示されるため、長期的な露出が期待できます。
成果を上げるには「テンポの良い短尺動画」と「トレンド活用」が欠かせません。興味を引けなければすぐに飛ばされてしまうため、冒頭からストーリー性やエンタメ要素で視聴者を惹きつける工夫が重要です。さらに流行の楽曲や人気フォーマットを組み合わせれば、フィードへの露出も増やせます。
くわえて、ハッシュタグチャレンジやインフルエンサーとのコラボは新規顧客の獲得に直結する施策です。広告を併用すればターゲット層を絞った効率的なリーチが可能となり、集客効果をさらに高められるでしょう。
YouTube
YouTubeは世界最大級の動画プラットフォームで、日本国内でも幅広い世代に利用されています。長尺コンテンツを蓄積できるため自然とSEOとの相性が良くなりがちで、教育系からエンタメまで幅広いテーマで「検索され続ける資産」として活用できる点が強みです。
成果を上げるには専門性やストーリー性を意識した長尺動画が効果的で、商品レビューやハウツー解説、セミナー配信は信頼度やブランド理解を深めます。さらにLIVE配信では視聴者とリアルタイムで交流でき、コメント欄を通じたエンゲージメント向上にも有効です。
チャンネル登録によるファン獲得やショート動画による拡散力も期待でき、広告では検索履歴を活用した高度なターゲティングが可能。ただし編集や構成などのスキルが必要となり、運用には一定のリソースが求められます。
目的別SNS運用のポイント

SNS運用は「誰に」「何を目的に」届けるのかによってアプローチが大きく変わります。目的を明確にすれば、運用の方向性やKPI設定も定まり、成果につながりやすくなります。ここでは代表的な3つの目的別に、運用のポイントを解説します。
ブランディング目的の場合
SNSをブランディングに活用する際は、短期的な数値成果よりも「企業の姿勢や世界観」を一貫して発信することが重要です。ビジュアルやトーンを統一し、ユーザーが「この企業らしさ」を感じられるコンテンツ設計を行いましょう。
具体的には、企業理念に基づいたストーリー投稿、社員紹介や働き方の発信、CSR活動の紹介などが効果的です。
- いいね数
- シェア数
- コメント数
売上拡大目的の場合
売上拡大を目的とするSNS運用では、購買導線を意識したコンテンツ設計が不可欠です。キャンペーン告知や商品紹介を投稿するだけでなく、リンク機能やショッピング機能を積極的に活用して購入ページへの移動をスムーズに設計しましょう。
また、クーポン配布や限定セールの情報は、購買意欲を刺激する有効な手段のひとつです。
投稿ごとの成果を継続的に分析・改善し、SNSを単なる集客ツールではなく、売上に直結する販促チャネルとして機能させることを意識しましょう。
- クリック数
- ECサイト流入数
- 購入件数
認知拡大目的の場合
認知拡大を目的とするSNS運用では、拡散性の高いコンテンツを計画的に投入することが鍵です。TikTokやInstagramリールなど短尺動画や拡散性の高いX(旧Twitter)は、非フォロワー層へのリーチに効果的です。
さらに、キャンペーン参加型のハッシュタグ企画や、時事性・トレンドを反映した投稿を取り入れることで、拡散力を高められます。また、インフルエンサーやユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用も有効です。
- インプレッション数
- リーチ数
- フォロワー増加数
SNS集客の成功法則に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
SNS集客の成功法則!5つの秘訣とSNS別アルゴリズムを徹底解説
複数のSNSを活用したマーケティング戦略

SNSはそれぞれ特徴が異なるため、単独での運用だけではリーチに限界があります。
複数のSNSを組み合わせることで、認知拡大から購買促進、ブランド育成まで一貫した流れを構築できるのが大きな強みです。ここからは代表的な組み合わせごとの戦略を紹介します。
TikTok&Instagram
TikTokとInstagramを組み合わせた戦略は、若年層への認知拡大と購買促進を同時に実現できる点が強みです。TikTokでは拡散力のあるトレンド動画や参加型コンテンツを発信することで短期間で幅広い層にリーチできます。
一方、Instagramは世界観を統一したビジュアルやストーリーズ、ショッピング機能によって、商品理解やファンの育成が強みです。たとえば、TikTokで話題化した動画をInstagramに再編集して配信すれば、購買導線を強化しつつブランドストーリーに沿った深い接触が狙えます。
さらに、両プラットフォームで共通のハッシュタグやUGCを展開することで相乗効果を生み、認知から購買までを一気通貫で支えるマーケティング施策を構築できるでしょう。
YouTube×Instagram
YouTubeとInstagramを組み合わせた戦略は、深い理解と即時のアクションを同時に促せる点が特徴です。YouTubeでは商品レビューやハウツー動画、セミナー配信などを通じて専門性と信頼性を訴求し、中長期的な検索流入を獲得します。
Instagramではリールやストーリーズを活用して、YouTube動画のプレビューや切り抜きを再編集・共有することで、瞬間的な関心を喚起し購買導線へと直結させられます。
さらに、Instagramのショッピング機能を組み合わせれば、動画視聴から購入までをスムーズにつなげられるのも強みです。両者を連動させることで、ブランドの世界観を維持しつつ、長期的な価値訴求と日常的な接点づくりを両立できる戦略が実現します。
Twitter&YouTube
YouTubeとX(旧Twitter)を組み合わせた戦略は、拡散力と検索性の相互補完が魅力です。X(旧Twitter)では新動画の公開告知やトレンドを絡めた短文投稿により、短期間で幅広いユーザーにリーチできます。
一方、YouTubeは長尺コンテンツの蓄積によって検索経由の流入が見込め、中長期的な視聴やファン形成につながります。たとえば、新商品レビュー動画をYouTubeに公開し、その要点をX(旧Twitter)で速報的に発信すれば、初動の再生数拡大と持続的な視聴獲得を両立可能です。
また、X(旧Twitter)上でのコメントやリポストを通じたユーザー交流は、YouTubeチャンネルへのロイヤリティ向上にも直結します。即効性と持続性を兼ね備えた有効なクロスプラットフォーム戦略といえるでしょう。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
SNSマーケティングが失敗するケース

SNSマーケティングは効果が高い一方で、計画や体制が不十分だと成果が出ず、かえってブランド価値を損なうリスクがあります。ここでは企業が陥りやすい失敗の典型例を紹介し、なぜうまくいかないのか、その背景を解説します。
SNS担当者への属人化リスク
SNSマーケティングが失敗する大きな要因の1つはSNS運用の属人化です。担当者にすべてを任せきりにすると、突然の異動や退職でノウハウが失われ、運用が停止するリスクがあります。
また、個人の感覚や経験に依存すると、投稿内容やトーンが一貫せず、ブランドイメージが揺らぐ恐れもあります。
適切な運用体制を築くためには、運用ガイドラインやコンテンツ方針を明確に文書化し、複数人で管理できる体制を整えることが重要です。属人化を排除し、チームで共有可能な仕組みを作ることで、長期的に安定したSNS運用が可能となります。
従業員の理解不足による失敗
SNSマーケティングは担当者だけで完結するものではなく、従業員全体の理解と協力が欠かせません。しかし社内でSNSの重要性が共有されていないと、社内から評価されずにSNS担当者のモチベーションの低下を招きます。
また、従業員が軽い気持ちで不適切な投稿を行い炎上を招いたり、協力が得られずコンテンツが不足したりする事例も少なくありません。これを防ぐには、運用の目的や方針を社内で明確にし、ガイドラインの策定や教育の徹底が不可欠です。
従業員一人ひとりがSNSを「自分ごと」として理解すれば、ブランド価値を守りながら発信力を高めることができます。
企画力不足・短期視点の弊害
SNSマーケティングは即効性があるように見えますが、実際には中長期的な戦略が欠かせません。短期的な成果だけを追い求めたり、場当たり的な企画を繰り返していたりすると、一貫性のない発信となり、フォロワーの信頼を得ることが難しくなります。
とくに「流行に乗るだけ」の投稿は一時的な話題にはなっても、ブランド価値の向上にはつながりにくいのが現実です。こうした失敗を防ぐには、年間を通じたテーマ設計や顧客ニーズに基づく企画を行い、短期施策と長期施策をバランスよく組み合わせることが重要です。
まとめ:SNSマーケティングの未来を見据えた運用が重要
SNSマーケティングは、単なる拡散や一時的な話題づくりにとどまらず、企業の成長戦略における重要な柱となっています。
InstagramやTikTokでの拡散力、YouTubeでの信頼構築、LINEでの顧客育成など、それぞれのSNSが担う役割を理解し、目的に応じて適切に組み合わせることが成果のカギです。
また、アルゴリズムやユーザー行動は日々変化しており、最新の動向を取り入れながら柔軟に対応する体制も欠かせません。
短期的な成果にとらわれるのではなく、ブランド価値や顧客との関係性を長期的に積み上げていく姿勢が、これからのSNS活用において不可欠といえるでしょう。未来を見据えた戦略的なSNS運用こそが、企業に持続的な成果をもたらします。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
【関連おすすめ記事】
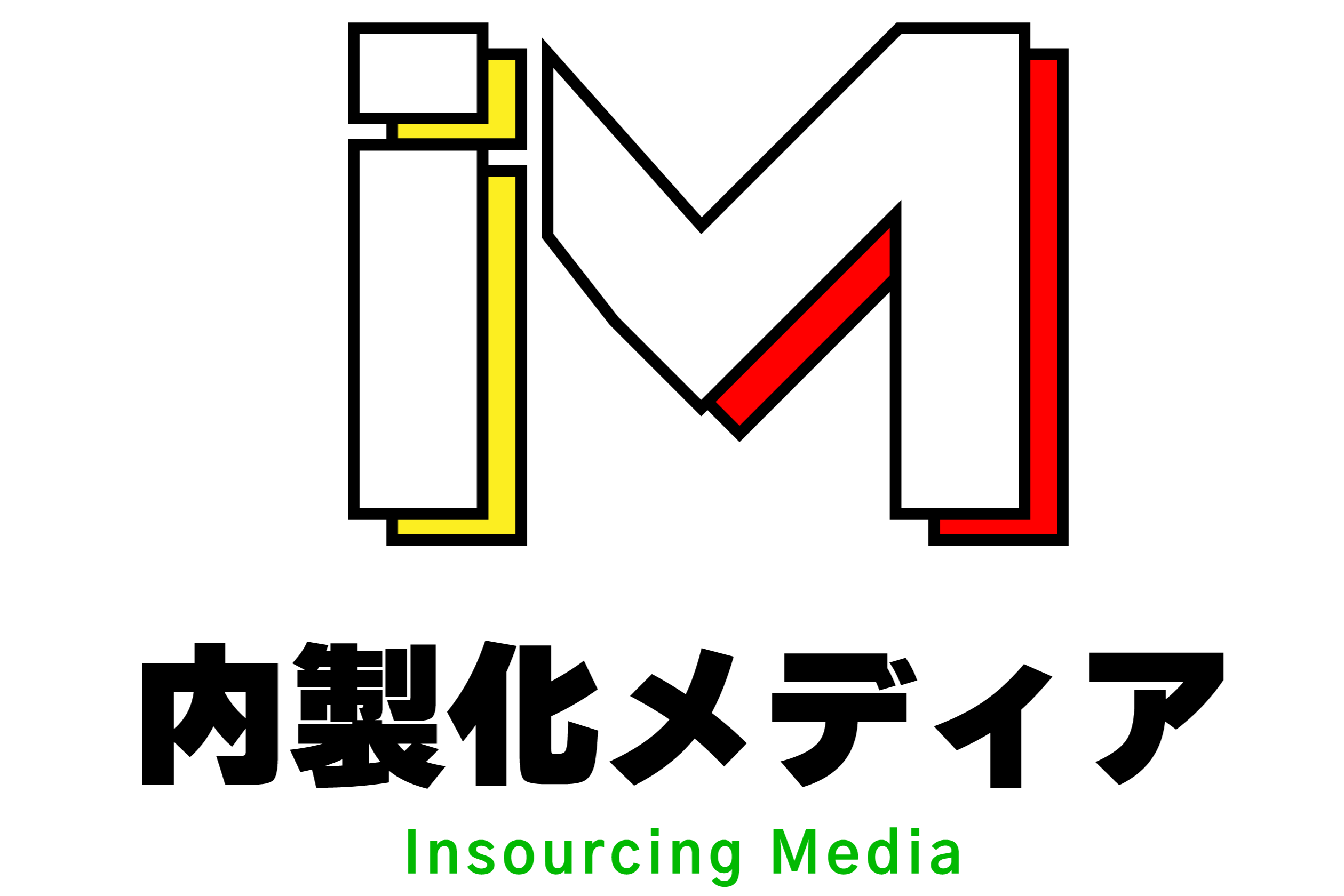
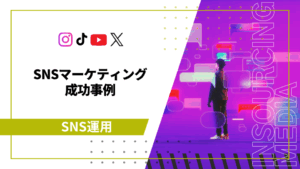








コメント