中小企業診断士はSNSに取り組むべき!集客方法と成功事例を詳しく解説

「中小企業診断士だけど、どうSNSすれば良いかわからない。」こうお悩みの人は多いのではないでしょうか?
従来、中小企業診断士のメインの集客方法は、紹介や口コミによるものでした。しかし社会のデジタル化が進みSNSの利用が爆発的に増えた現在は、中小企業診断士においてもSNSを活用した情報発信や集客が重要な戦略となっています。
本記事では、中小企業診断士がSNSに取り組むべき理由と、効果的な活用方法について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
SNSの集客方法に関して、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
⇒SNS集客の成功法則!5つの秘訣とSNS別アルゴリズムを徹底解説
※株式会社シュビヒロでは、幅広くSNSの運用代行が可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください
中小企業診断士がSNSに取り組んだ方がよい理由とは?

中小企業診断士がSNSを活用したほうがいい理由は、主に以下の3つです。
1つずつ詳しく見てみましょう。
信頼獲得に繋がりやすいから
SNSは従来のホームページと比べて、視覚的な訴求力が強く直感的な情報伝達力も高いものです。静的な印象のあるホームページよりもユーザーの関心を引きつけやすいメディアといえます。
またSNSでは継続して更新を重ねられるため、内容が固定されるホームページよりも多くの情報を視聴者に伝えることができ、知名度アップや信頼獲得に繋げやすくなります。
自らの分析力・課題解決力や業界理解の深さなどを示す具体例をSNSのコンテンツとして投稿することで、自身の実力や専門性を、従来よりもっとわかりやすく伝えることが可能です。
実際の支援事例や日常的な業務への取り組み、クライアントとの関わり方などをSNSを通じて継続的に発信すれば、中小企業診断士としての実績や個人的な人となりをアピールでき、視聴者(潜在顧客)の信頼を得ることができるでしょう。
また、経営に関する最新のトレンドや新しい制度改定への対応をタイムリーに情報提供することで、専門家としての価値をアピールすることもできます。
専門性のある発信で「選ばれる理由」を明確にできるから
SNSで自身の専門分野に関する情報を発信し続ければ得意分野での自身の専門性を繰り返しアピールでき、やがて「この分野ならこの診断士」という認識を得られるようになるでしょう。
すると得意分野の悩みを抱える視聴者に、「この診断士に相談したい」と思ってもらえるようになり、新規顧客の獲得に繋がります。
中小企業診断士として選ばれるために、SNSの投稿では、表面的な知識ではなく実務経験に基づく知見を述べたり、具体的な実践方法を提示したりすることが必要です。
また、最新の知識や技術を積極的に学んで投稿に反映していくと、視聴者の信頼度は増し、自身の専門家としての信頼度をあげることができます。
コンサル力の証明になるから
SNS上で画像や動画を使って複雑な経営課題をわかりやすく解説したり具体的な改善提案を示したりすることで、コンサル力をフォロワーに証明できます。
そのような投稿の定期的・継続的な発信により、潜在顧客に対し、どのように対応してもらえるかのイメージ提供が可能です。結果的に見込み顧客が実際の相談に至るハードルを下げる効果が期待できます。
また、フォロワーからの質問に対する適切な回答やコメントへの丁寧なやり取りを続ければ、コンサルタントにとって重要な、コミュニケーション能力や相談対応力も同時にアピールできるでしょう。
中小企業診断士が集客をするためのSNS活用のポイント
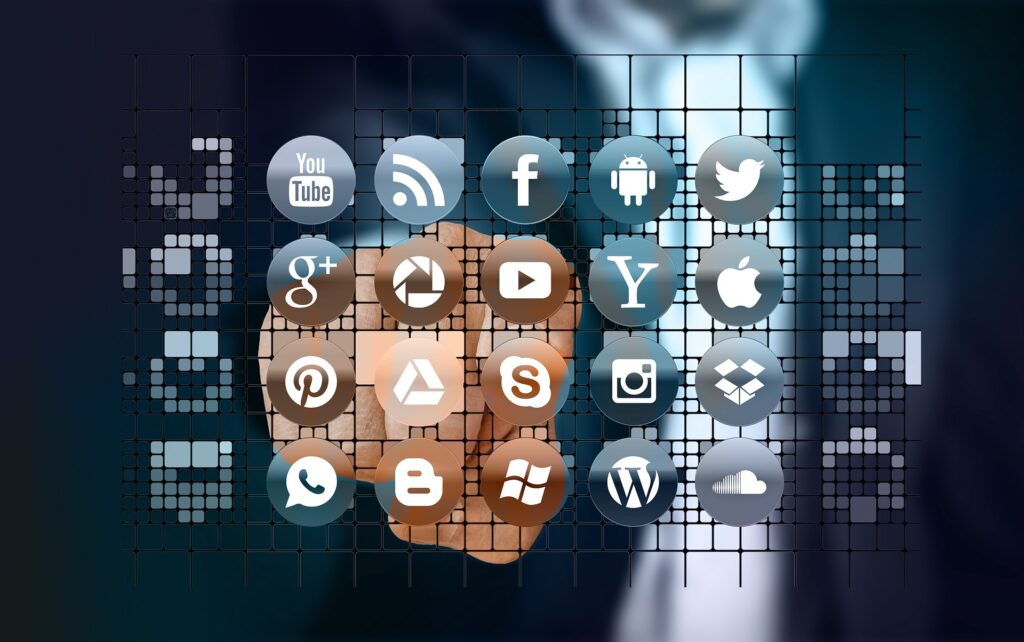
中小企業診断士が集客のためにSNSを活用する際、押さえておきたいポイントが存在します。以下のような点に留意してSNSを運営すれば、より集客の効果が高くなります。
- 専門分野を明確にする
- 図解や画像でわかりやすく解説する
- 守秘義務に配慮した上で実績を見える化する
それぞれ詳しく解説します。
専門分野を明確にする
中小企業診断士の業務範囲は広範囲にわたります。そのため、競合他社との差別化を図るために、自身の強みや得意分野を強く押し出した投稿をするのがおすすめです。
例えば、以下のような専門分野の設定が考えられます。
- 業界特化型:製造業、小売業、サービス業、IT業界など
- 機能特化型:マーケティング、財務改善、人事労務、事業承継など
- 規模特化型:スタートアップ、中小企業、地域密着型企業など
- 課題特化型:DX推進、働き方改革、SDGs対応など
専門分野を明確にすることで、ターゲットとする顧客層も明確になり、より的確な情報発信が可能です。
また、フォロワーも関心のある分野に特化したアカウントをフォローする傾向があるため、専門分野を強く打ち出したアカウントにすれば、エンゲージメントの向上も期待できます。
図解や画像でわかりやすく解説する
経営に関する専門知識は文章だけでは表現しにくいものですが、視覚的に伝えられるSNSではよりわかりやすい解説が可能です。
SNSでは図解、グラフ、イラストなどの視覚的要素を積極的に活用し、知識を視聴者によりわかりやすく伝えましょう。視聴しやすく理解しやすいコンテンツは、視聴者により納得され好まれる傾向にあります。
たとえば以下のような工夫が考えられます。
- 経営分析結果をグラフで表示
- 業務改善プロセスをフローチャートで図解
- 財務指標の推移をインフォグラフィックで表現
- 成功事例をビフォーアフターで比較
Instagramのような視覚特化型のプラットフォームでは、見やすく印象的なビジュアルコンテンツがユーザーの関心を引きやすく、拡散にもつながりやすいため、リーチ拡大に効果的です。Facebookでもビジュアルは重要な要素ですが、テキストやリンクによる情報発信との組み合わせが重視されます。
守秘義務に配慮した上で実績を見える化する
集客のためには過去の実績をアピールしたいところです。しかし中小企業診断士には守秘義務があるため、クライアントの情報を直接的に開示することはできません。
そこで次のような工夫をしてみるのがよいでしょう。
- 業界や企業規模を匿名化して改善事例を紹介する
- 数値はそのままでなく、概算値や比率で表現する
- 個別のケースを一般化して、課題解決手法のかたちで紹介する
これらの工夫により、守秘義務を遵守しながらも、実績を具体的に伝えることが可能です。
同様の課題を抱える企業にとっては、自社に置き換えてイメージしやすくなるため、次のアクション(問い合わせ・相談)へつながりやすくなります。
中小企業診断士と相性の良いSNSと活用方法

中小企業診断士と特に相性の良いSNSとその活用法について解説します。それぞれの特性を知った上で、どのSNSを運用するかを決定してください。
集客と相性がよいのはYouTube
中小企業診断士の集客と相性がよいものの1つがYouTubeです。動画コンテンツであるYouTubeは伝えられる情報量が多いため、中小企業診断士の深い専門知識を、直感的に分かりやすく説明できます。
概要欄に問い合わせ先などを明記することで、視聴者の相談への距離を縮めることができます。またコメント欄に寄せられる視聴者からの意見や質問に答えれば視聴者と直接的なコミュニケーションを取ることも可能です。
中小企業診断士のアカウントでは次のような内容の動画を提供するとよいでしょう。
- 経営分析の手法解説
- 業界トレンドの分析
- 中小企業の成功事例紹介
- 経営者向けの実践的なノウハウ
- 補助金・助成金の活用方法
またコメント欄に寄せられる声や質問を知ることは、潜在顧客が持つリアルな課題を把握できる機会でもあります。
名刺代わりになるFacebook
Facebookは実名登録制であるため、ビジネス用途での信頼性が高く、中小企業診断士にとって「デジタル名刺」としての役割を果たします。
Facebookはメインユーザー層が30〜50代とやや高年齢ですが、この年齢層は中小企業の経営者層と合致します。つまり他のSNSよりもターゲット層にリーチする可能性が高いということです。
また、InstagramやXなどより長文投稿が可能なため、中小企業診断士が取り扱う経営関連の話題を充分に伝えることができます。
さらにFacebookのイベント機能を使うことで、定期的な勉強会やセミナーの開催告知が簡単にできるようになり、フォロワーとより深い関係を結ぶ機会も作れます。
相談しやすい環境を作れるLINE
LINEは1対1のコミュニケーションを主とするため、顧客や見込み顧客との直接的なやり取りに適しています。
個別対応であり、さらにメッセージを送るのもごく簡単なため、顧客にとってLINEは気軽な相談がしやすい特徴があります。簡単にメッセージが送れるLINEの利便性を活かすために、顧客からは簡単な質問を受けたり初回相談の予約を受け付けたりといった活用をするとよいでしょう。
予約システムとの連携ができるLINEは、相談予約受付に適したプラットフォームです。
また、LINEを使用すれば定期的な経営情報の配信セミナーや勉強会の案内も、ユーザーにダイレクトに送ることができます。
仕事につながりやすいX(旧Twitter)
中小企業診断士を探している顧客がX(旧Twitter)上でハッシュタグ検索をして、ダイレクトメッセージで声をかけるケースは少なくありません。
そのためX(旧Twitter)は、適切に運用することで仕事の獲得に繋がるといえます。
またX(旧Twitter)はリポストが簡単なため、強い拡散力を持ちます。専門性が高く役にたつ情報だと判断されれば、投稿が非常に多くの人の目に触れるようになるでしょう。
リアルタイム性に優れるX(旧Twitter)では、経営に関する最新情報やトレンド、業界ニュースへの素早い対応が専門性のアピールに役立ちます。
企業のSNS運用に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
企業SNS運用の完全ガイド!成果を出すSNS運用手順と失敗しない体制作り
中小企業診断士のSNS成功事例4選

SNSを活用して成功している4人の中小企業診断士の例を紹介します。それぞれのアカウントの特徴を解説するので、自身のアカウント運営の参考にしてください。
X(旧Twitter):大石幸紀 中小企業診断士の日常

出典:https://x.com/ohishindanshi
大石幸紀さんはX(旧Twitter)上で、主に日常業務についての投稿をしています。書き手としてはあくまで中小企業診断士としてのスタンスを崩さず、プライベートな日常の様子は投稿しない一貫性があります。
時に中小企業診断士としてのキャリア経歴や経験、考え方などを語ることで人となりを表現すると共に、統一されたトーンでの投稿が専門家としての信頼感につながっています。
主に同業の中小企業診断士に向けての投稿が多めで、仕事の取り方や役立つ書籍の案内、ワーケーションのレポートなどに多くの反響を得ています。
またX(旧Twitter)上で、主催する勉強会の告知やレポートを行い、リアルなコミュニケーションの輪を広げています。特に勉強会の告知ではユーザーからの高い反応が見られ、X(旧Twitter)でのイベント告知の有効性を証明しています。
X(旧Twitter):秋田舞美

秋田舞美さんのアカウントは、中小企業診断士としての日々を、主にやわらかい文体で投稿している点が特徴です。
投稿は仕事を通じて感じたことから仕事上のエピソードまで多様で時には笑える内容もあり、人柄がにじみ出る親しみやすいトーンで語られるので楽しく読むことができます。
その面白さは秋田さんへの親近感を生むと同時に、このアカウントを続けて読みたいと訪問者に思わせる効果もあり、フォロワーを増やす要因になっています。
しかし柔らかさがある一方で、「中小企業診断士」としての視点を一貫して持ち続ける点ではブレがありません。この発信方針を保つことが、秋田さんの専門家としての信頼性を高めています。
投稿に時折「中小企業診断士としての本質的な視点」を盛り込むなど、1人の中小企業診断士の等身大の姿を投稿で表現することで、「話を聞いてみたい」「一緒に仕事がしたい」と思ってもらえるような、ユーザーとの距離の近さを構築しています。
YouTube:中小企業診断士 / 平井あずま

出典:https://www.youtube.com/@azumahirai
平井あずまさんはYouTubeチャンネルで、中小企業診断士の情報やマーケティングなど、ビジネスにまつわる内容の動画を配信しています。
中小企業診断士のための情報や知識のほか、中小企業診断士の稼ぎ方や診断士の実情など、視聴者の興味を引きやすい内容の動画が多いのが特徴です。
また中小企業診断士のリアルを見せるvlogも多く投稿しており、多数の視聴者獲得に成功しています。
YouTube:裏方診断士〜中小企業診断士の本音〜
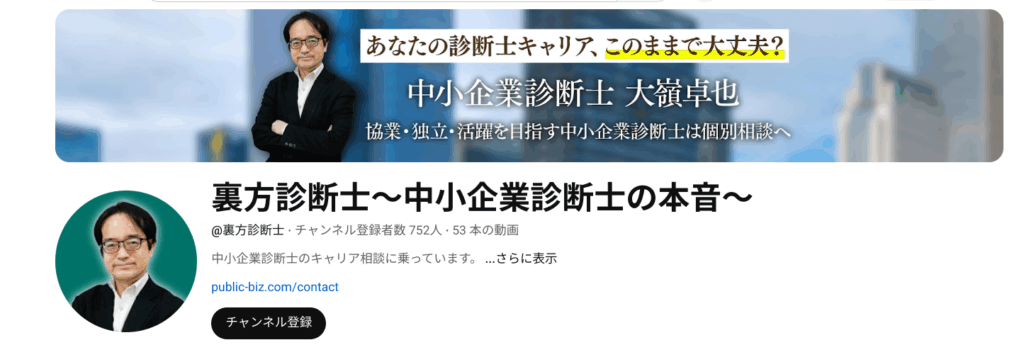
出典:https://www.youtube.com/@%E8%A3%8F%E6%96%B9%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%A3%AB
大嶺さんは自らの中小企業診断士の経験を基にして、中小企業診断士のキャリア相談を行っています。YouTubeチャンネルでもターゲットを中小企業診断士に絞り、中小企業診断士の仕事の取り方、役立つ最新情報、取るべきライセンスなど、実践的な動画を多く配信しています。
チャンネルの説明文では自らの経歴とともに相談窓口へのリンクを貼り、動画を見て相談したくなった視聴者がすぐにアクセスできる導線が用意されています。
視聴者に役立つ情報を提供して集客につなげている、好例の1つといえるでしょう。
中小企業診断士のSNS運用における3つの注意点

デリケートな案件にも関わる中小企業診断士がSNSを運用する場合は、次の3点に特に注意してください。
- プライバシーと守秘義務の遵守
- 発信内容とターゲットの整合を取る
- 信頼性のある情報発信を徹底する
プライバシーと守秘義務の遵守
中小企業診断士には守秘義務があり、クライアントのプライバシーを守らなくてはなりません。SNS運営においても、その点には厳重に注意を払う必要があります。
具体的には気をつけるべきなのは次のような点です。
- クライアント名や具体的な企業情報の開示になっていないか
- 写真や動画での無断撮影・公開をしていないか
- 相談内容や機密情報が漏洩する可能性はないか
- 間接的にクライアントや事例が特定されてしまう可能性はないか
守秘義務違反は、診断士としての信頼失墜だけでなく、法的責任も問われる可能性があります。最大限慎重に対応しましょう。
投稿前には内容をダブルチェックするなど万全の体制作りをおすすめします。
発信内容とターゲットの整合性を取る
専門性の高い内容を発信したとしても、ターゲットに響かない内容では高い集客効果は望めません。効果的なSNS運用には、発信内容とターゲット層の整合性が重要です。
よくある失敗例として、
- 専門的な内容が一般経営者に理解されるまでに噛み砕かれていない
- ターゲットが明確になっていない統一感のない投稿をしている
- 自己満足的な発信を続けている
などがあります。
失敗を避けるためにはまず、SNS運営に当たってのターゲット層を明確にする必要があります。そのうえでターゲットに響くような内容と伝え方を工夫しましょう。
ターゲットとする顧客層のニーズや関心事を常に意識し、価値のある情報を適切な形で提供することが、アカウントの成長と集客のためには大変重要です。
信頼性のある情報発信を徹底する
専門家である中小企業診断士は、常に正確で信頼のおける情報を発信する必要があります。
信頼性を確保するために、次のようなポイントを押さえておきましょう。
- 情報提供のソースは常に最新の法令や制度に基づくようにする
- 情報源や出典は慎重に選ぶ
- 推測や憶測での発信を避ける
- 万一誤った情報や古い情報を提供した場合は迅速に訂正や謝罪をする
信頼性の高い情報を発信し続けるためには、継続的な学習と情報更新が欠かせません。質の高い、信頼性のある情報発信を心がけることが、中小企業診断士としての成功につながります。
まとめ

本記事では、中小企業診断士がSNSを活用することのメリットと、メリットを最大限に引き出すためのポイントについて解説しました。
高い専門性を持つ中小企業診断士のSNS運営には、価値の高い情報発信を継続することが求められています。
中小企業こそSNS運用がおすすめという現代のビジネス環境において、診断士自身もSNSを効果的に活用することで、より多くの企業支援の機会を創出できるでしょう。
SNS運用にあたっては、自身での運用の他に、SNS運用代行会社に任せるという方法もあります。SNS運用のプロである代行会社は、経験に裏打ちされた知見とノウハウを持っているため、より効果的なSNS運営が可能です。
シュビヒロでは、YouTube、X、Instagram、TikTokなど多数のプラットフォームのSNS運用代行を月額5万円からの格安料金で承っております。これまでにも様々な業界の支援をさせていただき、多くの業績改善を実現した実績があります。
SNS運営をお考えの中小企業診断士様はぜひ1度、豊富な経験とノウハウをリーズナブルな料金で提供するシュビヒロへ、お気軽にご相談ください。
※株式会社シュビヒロでは、企業や経営者の方のX(旧Twitter)を運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
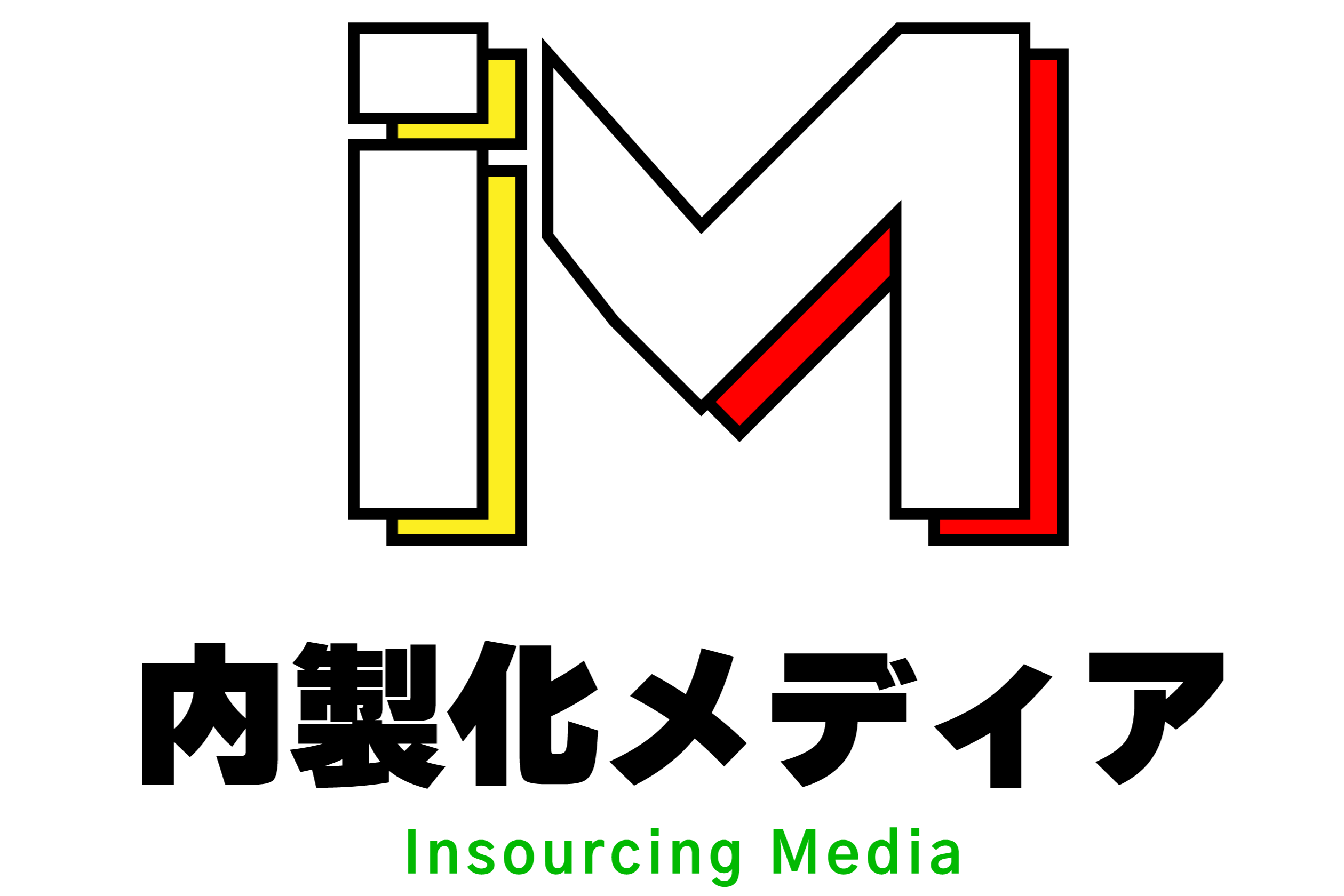




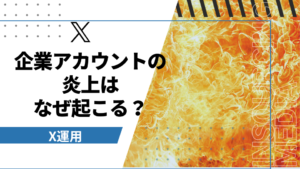
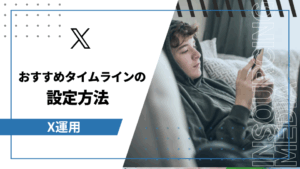

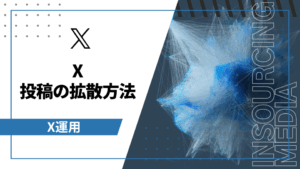
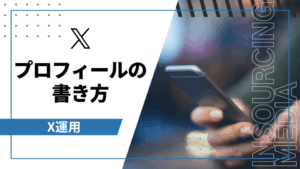
コメント