【学習塾】SNSを用いて集客する方法とは?効果的な活用法を解説!
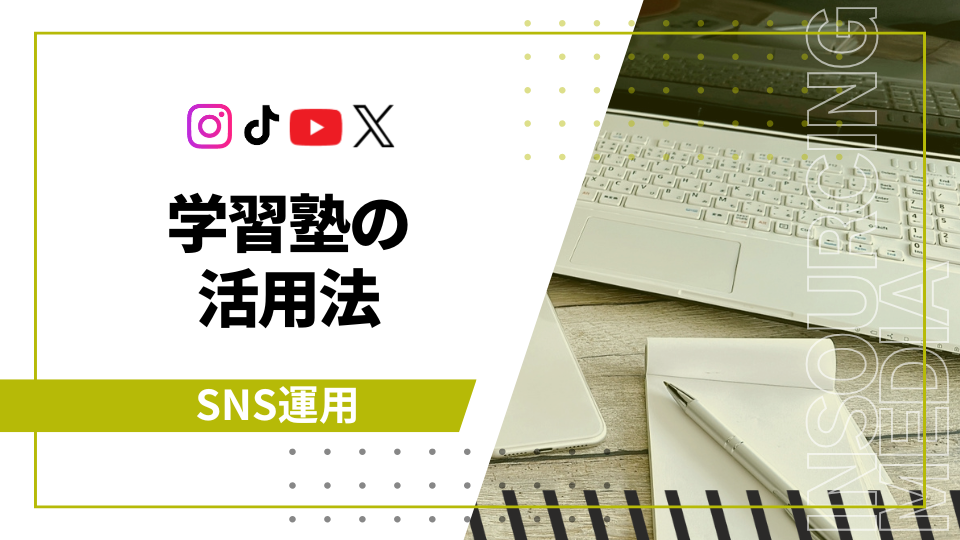
現代の教育市場において、学習塾の運営者にとってSNSを活用した集客は避けて通れない重要な戦略となっています。しかし、SNSの集客方法が分からず困っているという人も多いでしょう。
本記事では、学習塾がSNSをどのように活用すべきか、そしてその成功事例について詳しく解説します!
塾長や経営者の方々に、実践的かつ効果的なSNS集客のノウハウをお届けします。
SNSの運用代行に関して、相場や運用代行の概要を以下の記事でまとめています。詳しく知りたい人はぜひ合わせてご覧ください。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
学習塾の集客にSNS運用がおすすめな理由

まず、学習塾にとってSNS集客が重要である理由を理解することから始めましょう。うまく活用できれば非常に相性が良く、集客数の拡大に繋げられます。
塾や講師の雰囲気を自然に伝えやすいから
SNSで塾の勉強風景や講師のプロフィールなどの紹介をすることで、塾の雰囲気を伝えることができます。
また、日常的な投稿を続けることで、親しみやすい雰囲気を作り、入塾までのハードルを下げることができるでしょう。
とくに、講師の人柄や指導の熱意は、文字情報だけでは伝わりにくいため、動画の投稿が効果的です。
塾での楽しい学びの様子を写真や動画でリアルに伝えることで、この塾に通っている自分が想像しやすくなります。
さらに、成功事例や進学実績を投稿することで、この塾に通うことで将来的にどのような学校に進学できるのかイメージしやすくなり、入塾前のモチベーションアップにも繋がるでしょう。
公式サイトやチラシだけでは伝えきれない塾の魅力を、SNSを通じて自然に発信できるのが大きなメリットです。
ファン化しやすいから
SNSの強みは、ユーザーとの相互コミュニケーションができる点にあります。また現在のSNSの多くは、ユーザーが興味を持ちそうな投稿をおすすめとして自動で表示させる仕組みが採用されています。
そのため、継続的に投稿をすることで、たとえフォロワーでない人でも、潜在ターゲットに投稿が表示されるチャンスがあるのです。
また、何度も投稿を目にすることで親近感が湧き、「この塾が自分に合っているかも」と思われやすくなります。
塾に興味の合る見込み客をファンにするためには、以下のような発信を心がけましょう。
- 共感できる:講師や生徒の日常など、親しみを感じる内容を投稿する。
- 参考になる:効果的な勉強法や過ごし方など、役立つ情報を提供する。
- 信頼できる:講師の経歴や実績、専門知識を示して安心感を与える。
フォロワー数が少なくても、ターゲットに適した発信を続けることで、教室見学やお問い合わせにつながる可能性が高まります。SNSは単なる宣伝ツールではなく、塾のファンを育てる大きな武器になるのです。
無料で始められるから
塾の認知度を広めるためには、SNSだけでなく、紙媒体であるチラシが用いられることがあります。チラシのメリットは、手元に残るため、受け取った当人が興味を示さなくても、家族の誰かが関心を持つ可能性がある点です。
しかし、配布後はその効果を検証するのが難しく、効果が実感できるまで時間がかかります。また、チラシの作成には印刷料金やデザイン費、配布費用など、さまざまなコストが発生します。
一方で、SNSは基本的に無料で運用でき、塾の認知度を低コストで広げるための強力なツールです。SNSの魅力は、広告費をかけずに広範囲にリーチできる点で、アカウントの運営費用は主に人件費のみです。
さらに、運用しながら改善するPDCAサイクルをスピーディに回せるのもSNSの魅力。例えば、問い合わせ増加を目的とした投稿を複数用意してそれぞれの反応を比較する「ABテスト」や、データ分析をもとに次の投稿を改善することができます。
無料でありながら、スピード感を持った改善活動によって、少ないコストで効果的な宣伝が可能となるのは、SNSのメリットです。
保護者の不安を払拭できるから
保護者が子どもを塾に通わせる際、多くの不安を抱えているのが現実です。SNSを活用することで、保護者が普段は見ることができない塾の雰囲気や、講師の指導風景を発信できます。
保護者はお子様がどんな環境で勉強しているのかがわかるようになり、お子様の学びの様子をリアルに感じることができるでしょう。
また、実際に授業を受けている生徒の姿や、講師とのやり取りを紹介することで、保護者に「信頼できる塾だ」と感じてもらいやすくなります。
テストでの成績も改善されれば、「この塾で本当に良かった」と思ってもらえますし、口コミの広まりによって入塾を希望する生徒も増えること間違いありません。
学習塾におけるSNSの効果的な活用方法

SNSを運用する場合、その目的に応じたSNSを利用する必要があります。SNSごとに機能や強み、ユーザー層が異なるため、適切なプラットフォーム選びが重要です。
ここでは、以下の主要SNSについてその特徴やユーザー、運用のポイントなどをまとめていきます。
- X(旧:Twitter)
- YouTube
- TikTok
Instagramは、画像や動画を中心に情報を発信できるSNS。特にビジュアルで塾の魅力をアピールするのに最適な媒体です。
令和6年に総務省によって発表された「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、Instagramは全世代をとおして56.1%と年々増加傾向にあります。
また、塾のターゲット層となる10代のユーザーは72.9%、親世代である30代で68%、40代で57.2%と半数以上の利用率を誇り、女性のユーザーが多いのが特徴です。
24時間で消えるストーリーズやライブ配信など、機能が豊富で、目的に応じて使い分けることで効果的なSNSマーケティングが可能となります。
Instagramのでは、学習方法やアドバイスを視覚的なビジュアルコンテンツとして提供すると効果的です。また、ハッシュタグと呼ばれる機能をうまく活用することで、情報の拡散と見込み客の獲得ができます。
Instagramにおけるハッシュタグの活用方法では、地域名といくつかのニーズを組み合わせることがポイント。具体的にいは、以下のとおりです。
- 地域名+塾名
- 地域名+塾の特徴(個別・集団)
- 地域名+無料体験、夏期講習
- 地域名+中学受験、高校受験、大学受験
塾は学校帰りに通うケースが多いため、通えるエリアを示す地域名が重要となります。うまく組み合わせることで効率的に見込み客にリーチしていきましょう。
令和6年の総務省による「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、Facebookは30代の44.4%、40代は39.4%が使用するSNSであり、中高生のお子さんを持つ保護者層へのアプローチに適しています。
Facebookはビジネス目的の利用が多く、30代〜40代というと部長や課長などの役職がついているユーザーが多いでしょう。また、お金に余裕があり、お子様の教育にも力を入れたいと考えているユーザーが多いことが想定できます。
また、Facebookのビジネスアカウントは、検索エンジンの表示対象となります。つまり、塾のFacebookでビジネスアカウントを作成することで、塾について検索しているユーザーに表示される可能性が高まるということです。
Facebookでは、受験対策や保護者向けの長文コンテンツを発信することで、保護者の信頼を得やすくなり、集客にもつながります。さらに、ブログやYouTubeなど他のメディアに誘導することも可能で、相乗効果を狙った運用が可能です。
また、Facebookでは、コミュニティという機能があり、メンバー同士で情報を共有したり、質問したり、意見交換を行ったりすることができます。
塾がこの機能をうまく活用することで、生徒や保護者とのつながりを深め、信頼を築くことができるでしょう。
X(旧:Twitter)
X(旧Twitter)は、140文字以内の短文をメインとするSNSで、リアルタイム性と拡散力が高いのが特徴のSNS。
常に最新の投稿が表示される仕組みとなっているため、定期的な更新とターゲットの生活時間に合わせた投稿のタイミングが重要となります。
また、フォロワー数が少なくても、リツイート機能によって情報が瞬時に拡散する可能性があり、塾の認知拡大にも利用できるでしょう。
ハッシュタグでの検索機能なども揃っているため、フォロワー外のユーザーにもリーチしやすく、また継続して塾についての投稿をすることで、AIが自動でターゲット層におすすめとして投稿を表示をしてくれる可能性が高まります。
公式によると、2024年11月時点でのX(旧:Twitter)の国内月間アクティブユーザー数は約6,700万人に達しています。また、「モバイル社会研究所」の調査によると、特に10〜20代の利用率が共に70%を超えており、生徒層へのアプローチに適しているといえるでしょう。
学習塾での具体的な活用例としては、勉強に関するヒントや豆知識の発信、アンケートやキャンペーンを実施して認知度を高めるなどの方法があります。
また、講師の個人アカウントを作成して、実績や経歴、経験などを発信していくことで、講師自身のブランディングにもなり、特定の講師に教わることを目的とした入塾も期待できるでしょう。
YouTube
YouTubeは動画をメインとする世界最大のSNS。長尺動画の投稿が可能なため、ほかのSNSよりも豊富な情報を伝えられる点が強みです。
YouTubeの国内アクティブユーザー数は7,120万人以上(2023年)で、認知率は96.8%と非常に高く、特に若年層では約8割が利用しています。また、幅広い年齢層が利用しているため、生徒だけでなく保護者へのアプローチにも最適です。
投稿動画はチャンネル内に蓄積される仕組みで、長期間に渡って視聴されます。そのため、投稿直後だけでなく半年後や数年後にも再生され、継続的に視聴者のファン化を促進できるのがポイント。
学習塾のブランディングやマーケティングツールとして大きな可能性を秘めていることにくわえ、うまく活用することで収益化を目指すことも可能です。
また、人気の動画は1度だけでなく複数回見直されることもあるため、科目ごとの問題の解き方や間違えやすいポイントの解説、勉強の方法など、実践的なテーマの動画を投稿することで、複数回視聴してもらえる可能性があります。
YouTubeには、短尺動画を投稿できるYouTube ショートの機能もあり、60秒以内のコンテンツで手軽に情報発信が可能です。ショート動画は全世界で1日300億回再生されており、視聴者との接点を増やす大きなチャンスになります。
TikTok
TikTokは、2017年10月に国内でサービスが開始された比較的新しいSNSですが、若年層を中心に急速に普及し、主要SNSの一角を占めるまでになりました。
TikTokの特徴は、短い縦型動画を気軽に投稿・共有できる点にあります。スマートフォンで簡単に撮影・編集ができるため、動画編集に不慣れな人でも使いやすい仕様になっています。
2025年1月時点で、TikTokの国内月間アクティブユーザー数は約2,700万人に達しており、とくに10代~20代の利用が圧倒的です。つまり、生徒に直接アプローチしたい場合に有効なSNSといえるでしょう。
TikTokでは、トレンドに乗った投稿やハッシュタグを活用することで、より多くの生徒にリーチでき、塾の認知度向上につながります。
また、短時間でインパクトのある動画を投稿できるため、勉強のコツや豆知識、授業の雰囲気を伝えるコンテンツのほか、講師の個性を全面に出したユーモラスな投稿も注目されやすいでしょう。
塾のSNS運用が失敗してしまう要因
SNSは必ず成功するものではありません。しかし、正しく運用すれば大きく失敗することはなく、着実に成果が出るものです。
ここからは、学習塾のSNS運用が失敗する原因について解説していきますので、成果が出ずに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
事務的な発信しかしていない
学習塾のSNS運用が事務的な内容になっている場合、SNSを使いこなしているとはいえません。SNSはフォロワーとのコミュニケーションの場であり、一方的な情報発信ではターゲットの関心を惹きつけることができません。
SNSを成功させるためには、ターゲットニーズを満たすような投稿を心がけることが重要です。関係のない投稿が続くと、せっかく興味を持ってもらった顧客が離れてしまう恐れがあります。
また、事務連絡は新規顧客の獲得というよりは、既存顧客への情報共有が中心です。既存顧客の利便性向上のためには大切ですが、事務連絡に有益なコンテンツが埋もれてしまっては、SNSの強みである潜在顧客の獲得とは程遠くなってしまうでしょう。
投稿頻度にばらつきがある
SNSでは、最新の情報が求められます。過去に良いコンテツがあっても、1年間更新がされていない場合には、逆に不安要素となるでしょう。
また、SNSでは新しい投稿が上位に表示されるほか、更新のないアカウントは非アクティブアカウントとして表示の優先順位が下がっていきます。
そのため、定期的な更新が大切となります。一方で、1日に何本も更新する必要はありません。SNSごとの適切な投稿頻度を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。
YouTube:週2本
Instagram:週3本
TikTok:週3本
日記のようなアカウントになってしまっている
定期的な投稿ができていても、その内容がユーザーニーズを反映していない場合には、SNSは成功しません。
学習塾のアカウントでありながら、その投稿内容がお昼ご飯のことだったり、朝の出来事などの個人的で塾と関係のない内容に終止してしまうと、アルゴリズムは何の目的を持ったアカウントなのか把握できなくなる恐れがあります。
アルゴリズムが混乱すると、その投稿は有益でないと判断され、SNS上での評価を落とす原因となります。SNSの投稿内容については、SNS以下のポイントをよく考え、戦略的に運用することが重要です。
・ターゲットは誰か
・塾が解決できる課題は何か
・どんなコンテンツが求められているか
強みを活かせていない
SNS運用をする学習塾は多いですが、ありきたりな投稿では注目を集めることはできません。
認知度を高め、集客につなげるには、自塾の強みを明確にし、それを効果的に訴求することが重要です。強みを打ち出すことで競合との差別化が可能になり、ターゲットにとって比較検討の対象となります。
強みが明確であるほど選ばれやすくなりますが、特定のニーズに特化しすぎるとターゲットの母数が減り、十分な集客につながらない可能性がある点には注意が必要です。
例えば、A塾は「難関大学の合格実績」を強みとし、B塾は「1カ月で偏差値10ポイントアップ」を掲げている場合、B塾のほうが幅広い層の関心を引きやすいと考えられます。SNSで強みを訴求する際は、そのニーズの規模も考慮することが大切です。
学習塾の強みの具体例
実績:難関大学への合格率、偏差値の改善
指導力:ベテラン講師の在籍、講師の経歴
教材:オリジナル教材、受験の最新動向に沿った教材
料金設定:リーズナブル、成果報酬型、無料体験の有無
環境:集団授業での切磋琢磨、個別指導のきめ細かい対応
強みを活かしつつ、ターゲットのニーズに合った訴求方法を工夫することで、SNSを効果的に活用できます。
学習塾の集客に必要なSNS運用の基本
SNS運用では先にはじめるほどライバルよりも早く認知拡大ができる可能性が高まる一方で、ただ運用しているだけでは成功しません。
戦略やコミュニケーション手法など、あらかじめ理解しておくべきポイントが存在します。
- コンテンツ戦略の立案
- 投稿頻度とタイミング
- フォロワーとのコミュニケーション
- データ分析と改善
ここからは、塾がSNSをはじめるうえで必要なSNS運用の基本を詳しくみていきましょう。
コンテンツ戦略の立案
次に重要なのは、効果的なコンテンツ戦略の立案です。
ただ漫然と投稿するのではなく、計画的かつ戦略的にコンテンツを作成し、発信していくことが求められます。
まず、ターゲット層のニーズや関心事を深く理解することから始めましょう。
例えば、小学生の保護者であれば、学習習慣の形成方法や基礎学力の向上に関心があるかもしれません。
中学生の保護者であれば、受験対策や学習モチベーションの維持に興味があるかもしれません。
これらのニーズに基づいて、以下のようなコンテンツを計画的に制作し、発信していくことが効果的です!
・学習のコツや効果的な勉強法の紹介
・入試情報や教育トレンドの解説
・塾生の成功体験談や合格実績の紹介
・授業風景や塾の雰囲気を伝える投稿
・保護者向けの教育相談や進路指導のアドバイス
これらのコンテンツを、テキスト、画像、動画など様々な形式で提供することで、フォロワーの興味を引き付け、エンゲージメントを高めることができます。
投稿頻度とタイミング
コンテンツの質と並んで重要なのが、適切な投稿頻度とタイミングです。
投稿頻度が低すぎると存在感が薄れてしまいます。
また、投稿のタイミングも重要です。
多くの場合、平日の朝(7時〜9時頃)や夕方(17時〜19時頃)がアクセスのピークとなりやすいです。
ただし、これは一般的な傾向であり、実際には自塾のフォロワーの行動パターンに合わせて最適なタイミングを見つけていく必要があります。
フォロワーとのコミュニケーション
SNSの大きな特徴は、双方向のコミュニケーションが可能な点です。
この特性を活かし、フォロワーとの積極的なインタラクションを心がけましょう。
具体的には、以下のような取り組みが効果的です。
・コメントへの迅速かつ丁寧な返信
・フォロワー参加型の企画(例:クイズや川柳コンテストなど)の実施
・生徒や保護者の声の紹介(承諾を得た上で)
これらの取り組みを通じて、フォロワーとの信頼関係を構築し、コミュニティ感を醸成することができます。
結果として、口コミによる新規生徒の獲得や、既存生徒の継続率向上につながります。
データ分析と改善
SNS集客の効果を最大化するためには、投稿のパフォーマンスを定期的に分析し、改善していくことが不可欠です。
各SNSプラットフォームが提供する分析ツールを活用し、以下のような指標を定期的にチェックしましょう
・フォロワー数の推移
・投稿ごとのリーチ数とエンゲージメント率
・クリック数や問い合わせ数などのコンバージョン指標
・フォロワーの属性(年齢、性別、地域など)
これらのデータを基に、どのような投稿が効果的だったか、どの時間帯に投稿すると反応が良いかなどを分析し、継続的に戦略を改善していきましょう。
企業のSNSに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
企業SNS運用の完全ガイド!成果を出すSNS運用手順と失敗しない体制作り
学習塾のSNS集客成功事例
ここからは、学習塾が運営するSNSのうち、集客に成功している事例を紹介していきます。どういったコンテンツを投稿するのが良いのか参考にして、自社の運用にうまく取り入れてみましょう。
医学部専門予備校 京都医塾

出典:kyotoijuku
京都医塾は、医学部合格を目指す専門の学習塾です。「偏差値40から医学部合格」を掲げ、独自の指導法で多くの生徒のサポートをしています。
Instagramを活用した情報発信にも力を入れており、フォロワーは1.9万人、投稿数は1256件。投稿の中心はクイズ形式の動画で、楽しみながら知識を深めることができます。
また、実際に医学部に合格した生徒の体験談や、受験会場までスタッフが送迎する様子など、受験生のリアルを体験できる投稿が特徴的です。
さらに、講師のプロフィールや卒業生との交流の様子を定期的に紹介し、塾の温かい雰囲気を伝えています。和気あいあいとした投稿からは、学ぶことの楽しさや仲間と切磋琢磨する魅力が伝わってくるでしょう。
京都医塾ユニークな点は、勉強以外のリフレッシュ要素も大切にしていることです。グルメ紹介や観光スポット巡りなど、リフレッシュにつながるような投稿も多く、受験生のメンタル面でもサポートしている様子が伺えます。
ラオ先生

出典:@lao_teacher
ラオ先生は、横浜でイーロン個別進学塾の代表を務めながら、自らYouTubeやTikTokなどのSNS運用をしている教育系のインフルエンサー。いつも明るく元気な授業スタイルと、分かりやすい解説が魅力です。
TikTokでは2023年2月時点で累計再生回数3億回、累計800万いいねを獲得し、メディア出演もこなす実力派講師として知られています。
投稿内容は、学生に役立つ勉強法や知識が中心で、多くの学生から支持を集めています。YouTubeのフォロワーは30万人、Instagramは8万9000人、TikTokでは42万7800人のフォロワーを誇る日本を代表する教育系インフルエンサーです。
ラオ先生自身が質問に答えたり、問題の解き方を教えたりする動画を多数投稿しており、そのユニークなキャラクターも人気の理由のひとつ。
教育者としての経歴も申し分なく、多くの信頼を集める存在で、「一度は教えてもらいたい講師」として注目を集めています。
坪田塾

出典:@tsubotajuku
坪田塾は、「ビリギャル」のモデルにもなった実力派の学習塾です。「個別」を超えた「子」別指導を掲げ、大学受験と高校受験を専門としています。心理学をベースにした学習方法を取り入れ、「教えない指導」が評判です。
YouTubeでは、ユーモアたっぷりに解説している問題の解き方や暗記のコツが人気を博し、フォロワーは1.9万人に上ります。また、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などのSNSも積極的に運用し、多角的なSNSマーケティングを実施しています。
各SNSの特性に合わせたコンテンツ作りも特徴的で、YouTubeでは実際の授業のような講師による解説動画を投稿。一方、Instagramでは、ビジュアルにこだわった統一感のある投稿を意識し、魅力的なコンテンツを提供しています。
武田塾

出典:@takedajuku
武田塾は、授業を行わず自主学習に重点を置く独自のカリキュラムが特徴の学習塾です。YouTubeでは、「受験に役立つ情報を出し惜しみせず発信する」という方針で運営されています。
毎日1日2回の動画投稿を継続し、総コンテンツ数はすでに7,000本以上に達し、2021年4月には総再生回数1億回を突破し、多くの学生に視聴されている人気YouTubeチャンネルに成長しています。
さらに、LINE、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNSも効果的に活用し、地域ごとのアカウントも運営。地域に根ざしたマーケティングを強みとし、全国の受験生に向けた情報発信を続けているのも人気の秘訣です。
まとめ
SNS運用は、いまやあらゆる事業における集客に必須となっています。今回ご紹介した学習塾においても、認知拡大や顧客獲得にSNS運用はとても有効な手段です。
学習塾でのSNS運用では、入塾する学生を基本的なターゲットとしつつ、親御さんへの信頼を獲得できるようなコンテンツ制作が求められます。
コンテンツの具体例としては、以下のような内容が効果的でしょう。
- 学習のコツや効果的な勉強法の紹介
- 入試情報や教育トレンドの解説
- 塾生の成功体験談や合格実績の紹介
- 授業風景や塾の雰囲気を伝える投稿
- 保護者向けの教育相談や進路指導のアドバイス
また、活用するSNSによってコンテンツの内容や魅せ方は工夫必要があります。コンテンツ制作のノウハウやスキルがなくて悩んでいる場合には、運用代行の利用を検討するのもおすすめです。
シュビヒロでは、YouTubeをはじめ、Instagram、X(旧:Twitter)などの各種SNSのノウハウを十分に活かしたコンテンツ運用を、月額5万円から依頼可能!
SNS運用に課題を感じているものの、忙しくて手をつけられていないという方は、気軽に問い合わせてみてください。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のSNSを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
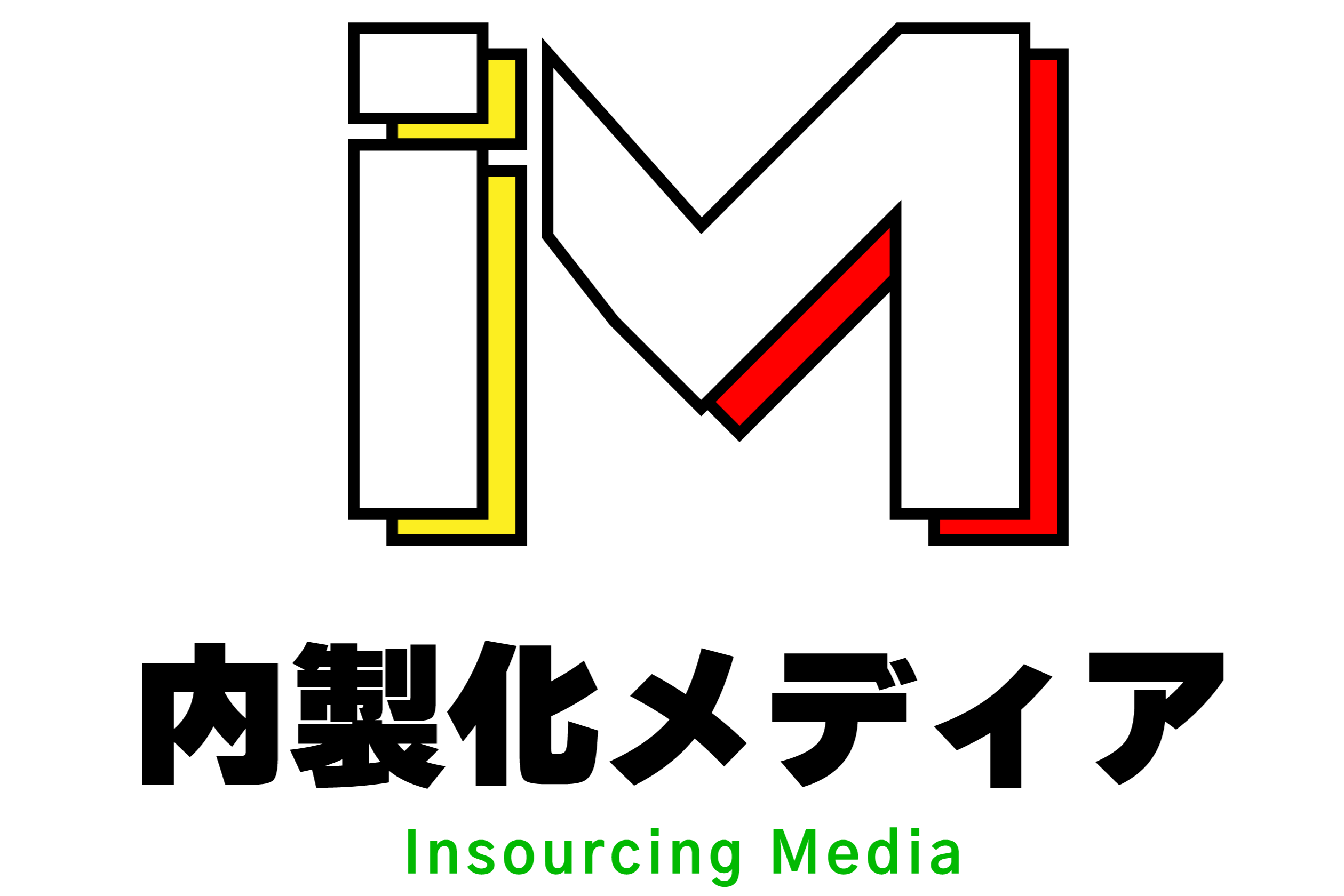
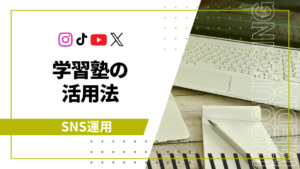




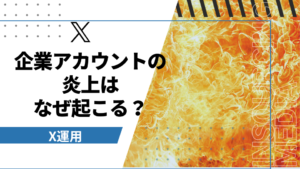
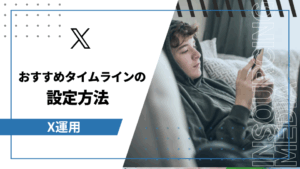

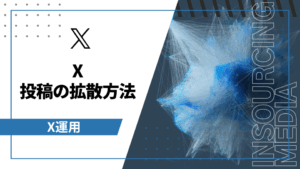
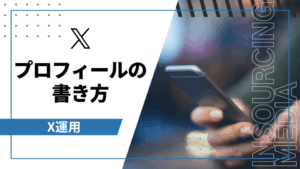
コメント