企業アカウントの炎上はなぜ起こる?実際の事例を検証し炎上リスクを抑える方法まで解説
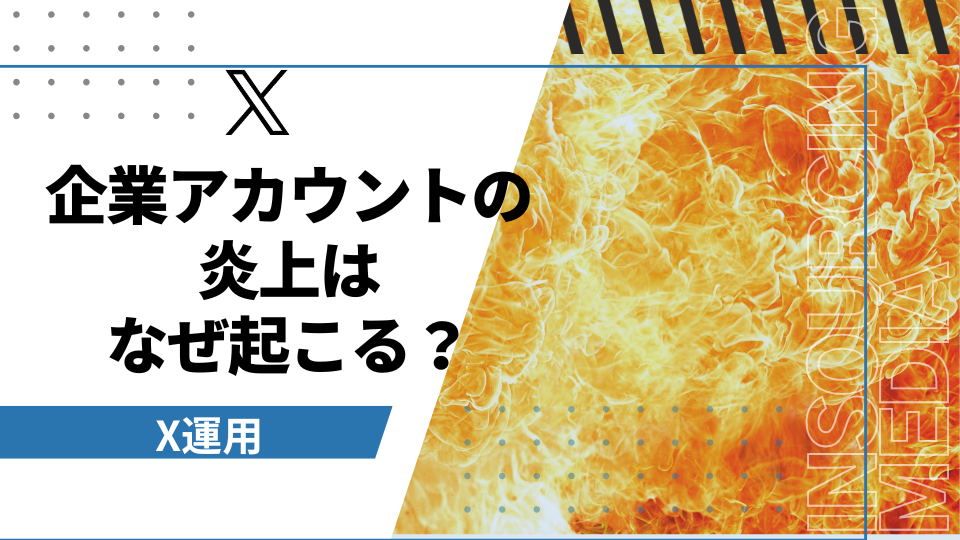
Xの企業アカウントが炎上しないか不安な方や、どういった運用をすると炎上リスクがあるのか気になっている方は多いのではないでしょうか?
ユーザーの数が大変多く拡散性の高いXは、企業の認知度を高めブランド力を強めるためにとても有効なツールです。しかしその拡散性の高さから、1度悪い評判が立つとあっと言う間に大きく広がってしまいいわゆる炎上を招くリスクも潜んでいます。
この記事では実際の事例をもとに炎上が起こる原因を明らかにし、炎上回避の方法を解説します。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のXを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
SNSの運用代行に関して、相場や運用代行の概要を以下の記事でまとめています。詳しく知りたい人はぜひ合わせてご覧ください。
企業のX運用における炎上とは

「炎上」とは、Xの投稿に関して不適切と見なす意見が集中し、強い批判や非難の嵐が起こる現象を言います。
かつては口コミや噂に限定されていた企業批判が、Xのような即時性の高いプラットフォームでは秒単位で日本中はおろか世界中に拡散され、以前とは比べ物にならないほどの破壊力をもつようになっています。
この炎上が起こると企業のブランドイメージに致命的なダメージを与える可能性があり、実際に廃業に追い込まれる企業例も見られます。
企業がXを運営する際には、炎上を予防する入念な方法と共に、万が一炎上した場合に備える対応策も準備しておかなくてはいけません。
Xで炎上が起こりやすい理由
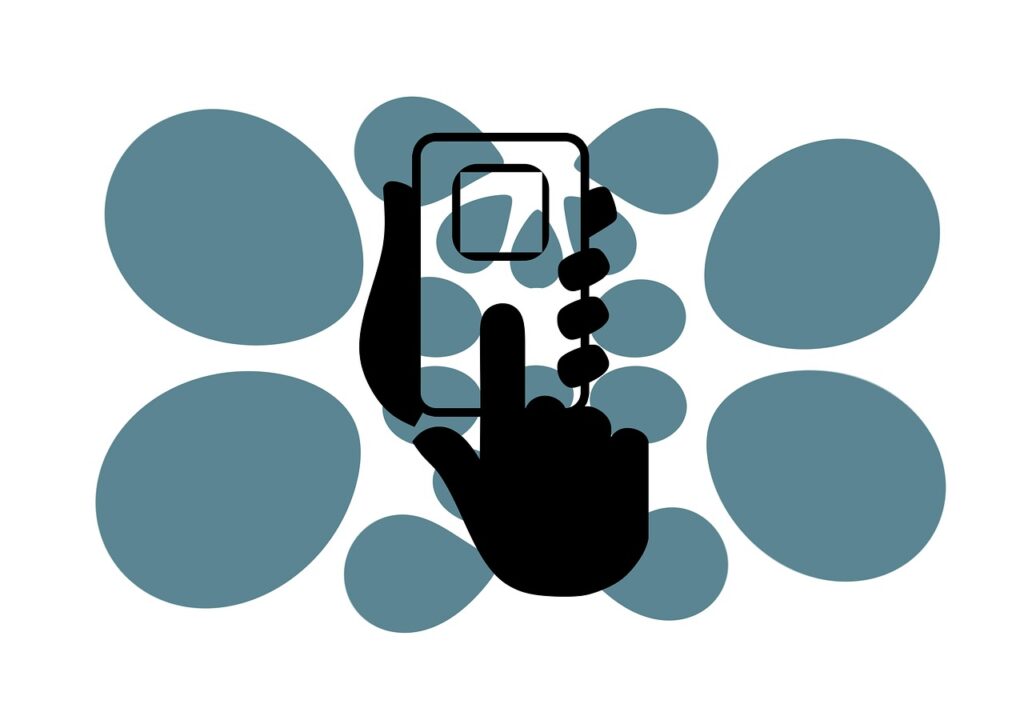
さまざまなプラットフォームにおいて炎上のリスクはありますが、Xでは特に炎上が起こりやすいと言われています。
その理由として以下のような要因が考えられます。
ユーザー数が多い
Xの国内利用者数は6700万人と言われ、これはSNSの中ではLINE、YouTubeに次ぐ第三位であり、オープン型SNSメディアの中では最多数です。
ユーザー数が多いということは、投稿が多くの人の目に触れやすいということであり、不適切な投稿は瞬時に世界中に広がり多くの人に読まれてしまいます。
また、不適切な投稿に関する批判や非難の投稿も、多数の人に行き渡りやすいということです。否定的な意見に共感する人が多ければ、すぐに炎上という事態になってしまいます。
匿名性がある
XはFacebookなどと比べて匿名性が高いSNSです。
実名を明かさずに意見を述べられるXでは、批判的な意見も書き込みやすくなります。
容赦のない批判や厳しい言葉、時には過激な文章も、匿名で投稿できるXでは比較的容易に投稿できてしまいます。
コメント・シェア機能がある
Xはシェアが容易であり、拡散機能にすぐれているSNSです。そのためいわゆる「バズり」が起きやすいツールでもあり、良い情報も悪い情報もたちまち多くの人の手で連鎖的にどんどん拡散されていきます。
また匿名でコメントを残すのも容易であるため、ネガティブな意見の書き込みがされれば多くの人の目にふれ、それに追随しようとする人が続出する例も見られます。
サイバーカスケード現象が起こりやすい
サイバーカスケード現象とは、先鋭化した意見を言っているのは実は少人数であるにも関わらず、その意見が大多数の人のものであると誤解してしまう現象のことです。
Xで実際は一部の人間による執拗なバッシングが起きているだけなのに、世の中の大多数が同じように集中攻撃をしていると錯覚してしまうのもサイバーカスケード現象の一例です。
その結果大多数の意見に同調しようとするユーザーが、「みんながやっているから」という理由で誹謗中傷や批判・非難に加担する場合があり、炎上に繋がります。
企業アカウントが炎上する主な原因

企業アカウントが炎上する原因は様々です。たとえば以下のようなものが過去に炎上を引き起こしています。
不適切な表現の使用
何の気なしに使った言葉や、普段から会話で使っている言葉でも、ネット上という公衆の場では不適切と捉えられることがあります。
差別的・侮蔑的など明らかに不適切な表現はもちろん、一般的に使われている言葉でも、企業のX投稿で使用すると批判の対象になるケースが見られるため、使用する言葉には注意が必要です。
クレーム対応の失敗
企業や従業員の、クレームに対する対応が十分でなかった場合も炎上の原因になります。
この場合は企業の投稿内容が問題になるわけではありません。しかしたとえばクレームへの対応に不満をもったユーザーがその不満をX上に投稿すれば、それはたちまち拡散され、企業が批判の的となる可能性があります。
競合他社批判
自社をアピールするために競合他社を批判・軽視するような投稿をするのも批判の的となります。
他社の商品やサービスを貶めたり低く評価するなどの投稿は却って自社への非難の原因となり、自社の評判や品位を落とすものです。
操作・投稿ミス
担当者が個人のアカウントと企業のアカウントを間違えて、本音や内部告発、精査されていない意見などを公式アカウントに投稿してしまう事例が少なくありません。いわゆる「誤爆」と言われるものです。
個人ならば見逃されるような言葉や内容でも、公式アカウントに投稿されてしまうとたちまち非難の的になる可能性があります。
安易なバズりの狙いすぎ
Xではバズりを狙いたいものですが、バズりを起こそうとするあまり、不適切な投稿をしてしまうと批判の対象になります。
商品やサービスと関係のないトレンドを繰り返し投稿したり、あえて過激な内容や言葉を使って投稿したりする行為は逆効果になりがちです。
トレンドには企業が便乗するにはふさわしくないものも含まれていますので、活用する場合にはくれぐれも注意が必要です
悪質な第三者のなりすまし投稿
企業に落ち度がない場合でも、悪質な第三者がなりすまし投稿をしてしまう場合もあります。従業員であると名乗っておいて、内部告発的な企業批判やその他不適切な投稿を繰り返すケースです。
なりすましの被害にあった場合は、慎重かつ迅速な対応が求められます。
企業アカウントが炎上した事例を4つ紹介

企業アカウントの炎上事例を紹介します。以下のような投稿で実際に炎上が起きています。
Xを運営する場合は以下のような投稿は避けるよう対策を取っておきましょう。
不適切な表現事例
某社の公式アカウントで『社畜さんいわく、残業のことを「二次会」って言うんだって♪そう言うとなんかすごく楽しそうな感じがするねっ二次会がんばって!ぼくはもう寝るよ~』という投稿が炎上しました。
「社畜」という言葉が企業の公式アカウントで使うには不適切だという批判が集まったのです。
ユーモアを狙った冗談半分での投稿だとしても、使用する言葉にはじゅうぶんな注意が必要です。
プライバシーへの配慮不足事例
某不動産会社の従業員が、有名人の来店や紹介物件などをポストしてしまいました。この投稿は直ちに炎上し、会社は投稿を削除したうえ謝罪しています。
従業員本人の投稿ではないのですが、従業員が有名人の情報を家族にもらしてしまい、その家族がポストしてしまい問題になった例もありました。
芸能人・有名人の情報に限らず、個人情報に繋がるような内容を投稿するのは厳禁です。
社会情勢への無配慮事例
某テーマパークのアカウントが、8月9日の原爆投下から70年目の節目の年に、「A VERYMERRY UNBIRTHDAY TO YOU!」のメッセージが入った、キャラクターの画像を投稿しました。
そのポストにはメッセージを意訳した「なんでもない日おめでとう」という言葉も入っていましたが、当日が長崎の原爆の日だったことから非難が殺到し、ポストの削除と公式サイトでの謝罪に発展しています。
投稿内容が問題となった事例
某老舗タイツメーカーがタイツの日にちなみ「ラブタイツ」キャンペーンをXで展開しました。
十数名のイラストレーターが#ラブタイツのハッシュタグをつけてイラストを投稿しましたが、スカートをたくし上げたり盗撮されているようなアングルや描写が散見されたことから「タイツを使用する女性目線ではなく男性目線」「タイツやストッキングを性的指向のものとしか見ていない」など批判が殺到しました。
さらにイラストに対し公式が「素敵なイラストばかりで、動悸がおさまらない中の人。みんな……めちゃくちゃ可愛くないですか………」とつけてリツイートしたこともあり大炎上に発展、企業は謝罪文書を出しキャンペーン中止とポストの削除、公式アカウントの一時閉鎖を行っています。
炎上が発生した場合の対応方法

万一炎上が発生してしまった場合には、迅速かつ適切な対応が必須です。
炎上への対応を失敗するとますますダメージが大きくなり、致命的ともいえる状態に陥る危険があります。
炎上してしまった時にやるべき対応方法は以下のとおりです。
事実確認
炎上にはさまざまな種類や原因があります。そのため、炎上してしまったらまず状況の正確な把握に努めましょう。
何が問題になっているのか、どのような経緯で炎上したかを明らかにします。また炎上の範囲についても調査・確認が必要です。
Xの中でエゴサーチやハッシュタグ検索をしたり、他のSNSを検索したりといった方法で事態を確認することで、次にやるべき対応策が明らかになります。
速やかな説明・謝罪
炎上に対しては速やかな説明・謝罪が不可欠です。
トラブルに直面すると隠したいという気持ちが起こるかもしれませんが、ごまかしや対応の遅れはさらなる炎上や批判を招きます。
批判を受けた投稿を黙って削除したり反論や言い訳をしたりするのも世間の印象をさらに悪くします。投稿に問題がある場合は、取り消し線を用いて問題部分を訂正し、企業アカウントで謝罪を行いましょう。
企業の責任ではない場合であっても、まずは炎上を起こしたということに対しての謝罪を行うことが大切です。
風評被害には削除依頼や法的処置を
炎上が第三者の投稿によるものでありかつ内容が事実ではない、いわゆる風評被害の場合は、投稿の削除依頼や法的手段を考えましょう。
投稿の削除は該当の投稿が公開されているメディアの運営者に依頼します。削除依頼に応じてもらえない場合は法的手段に訴えることもできます。
投稿が名誉毀損や誹謗中傷に当たるケースでも法的手段を検討しましょう。同時にこの炎上が風評被害であることを積極的に発信するなどの対応も必要です。
企業がSNSの炎上を防ぐ5つの施策

企業アカウントでは炎上を防ぐ施策が大変重要です。
炎上が企業に与えるダメージは甚大なものです。Xのアカウントを炎上させないために、普段から次のような施策を実施しましょう。
SNSのリテラシー研修の徹底
炎上防止のためにはXを始めとするSNSへの深い理解が必要です。リテラシー研修を徹底し、Xの特性や炎上を引き起こす原因・経路・事例などを学び炎上のリスクをできる限り小さくしましょう。
どういったものが不適切とされる可能性があるのかを知っておくのは大変有効です。
また企業のSNSガイドラインを作成して全社で共有し、浸透させておくことも大切です。
複数人によるチェック体制
Xの投稿は1人の担当者に任せるのではなく、投稿前に内容を複数人でチェックすることで炎上のリスクを軽減できます。
投稿に対する受け取り方は個々人で異なります。担当者には問題と感じられない投稿でも、第三者が見れば問題のある表現や内容かもしれません。
また1人の担当者のみが運営していると、バズりやいいねを狙って内容が過激になるケースも少なくありません。
投稿を複数人でチェックすることで多様な視点から投稿内容を精査でき、不適切ではないか誤解を招く表現がないか不快に思う人はいないかなどを確かめられます。
「誤爆」を防ぐアカウント管理
担当者が誤ってプライベートな内容や個人的な意見を投稿してしまう「誤爆」を防ぐために、担当者個人のアカウントと企業の公式アカウントはきちんと切り分けて運用する必要があります。
公式アカウント専用のスマートフォンを用意したり公式アカウントは会社のパソコンでのみ操作できる環境を整えるなどを実施し、誤爆のリスクを最小限にとどめましょう。
リスク対応フローの策定
Xは拡散力の高いSNSなので、炎上の火種を見つけたらできる限り迅速に対応しなければさらに炎上が広がってしまいます。
素早い対応ができるように、事前に炎上の火種を見つけた場合の対応マニュアルを用意しておきましょう。
対応フローや役割の明確化を行い、炎上シミュレーションも行って、適切な対応が迷いなく行える体制を整えておくことが大切です。
外部専門家の活用
炎上を防ぐためには、運営を代行会社に依頼したり、炎上対策の専門業者の力を借りたりするのもよいでしょう。
知識・技術・経験のあるプロのサポートを受ければ炎上のリスクを大きく軽減することができます。
また実際に炎上が起こってしまった場合にもケースの応じた適切な対応が期待できます。
Xの運用に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
X(旧Twitter)運用のコツ24選|フォロワー・反応・成果が伸びる実践テクニック集
まとめ
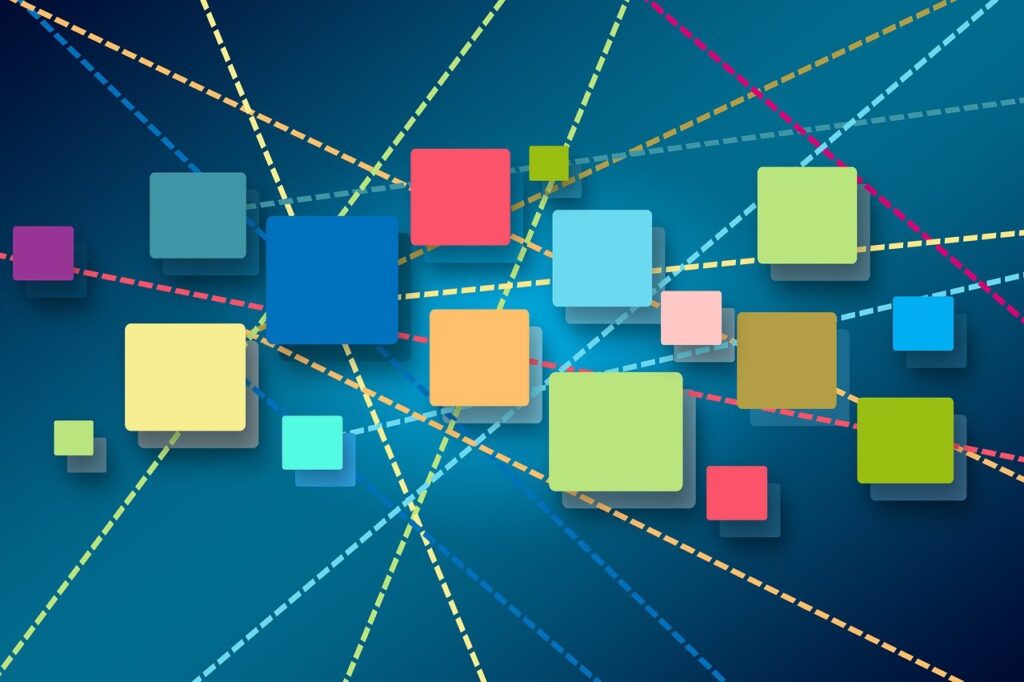
Xは拡散力と匿名性も高いため1度炎上するとその影響が広がりやすく、企業にとって致命的ともいえるダメージを与える可能性があります。
しかし利用ユーザーが多いXはリアルタイム性が高く、投稿が多くのユーザーに広まりやすいため企業の認知度を高めるためにとても有効なSNSです。
炎上リスクを恐れてXでの情報発信を避けるよりは、チェック体制の整備など炎上リスクを可能な限り抑える対策をしながらXをうまく活用する方が得策といえるでしょう。
また、炎上リスクを軽減するために外部の専門家に委託することもおすすめです。X運営を知識や見識のあるプロの運営代行会社に任せれば、炎上のリスクを可能な限り軽減しつつ情報発信ができます。
シュビヒロではXをはじめ各種SNSの運用代行を格安で承っています。
フランチャイズ関連・飲食・ECなど様々な業態の会社を支援し企業様の業績アップに貢献した豊富な実績とノウハウをもとに、可能な限り炎上リスクを抑えつつXの有効活用を図ります。
費用は月5万円から、毎日投稿用の記事草案を提供しXコミュニティへの参加資格も取得可能です。
Xの活用をお考えの企業様は、ぜひ1度ご相談ください。
※株式会社シュビヒロでは、企業様のXを運用することが可能です。ご相談したいことがございましたら、フォームよりお問合せください。
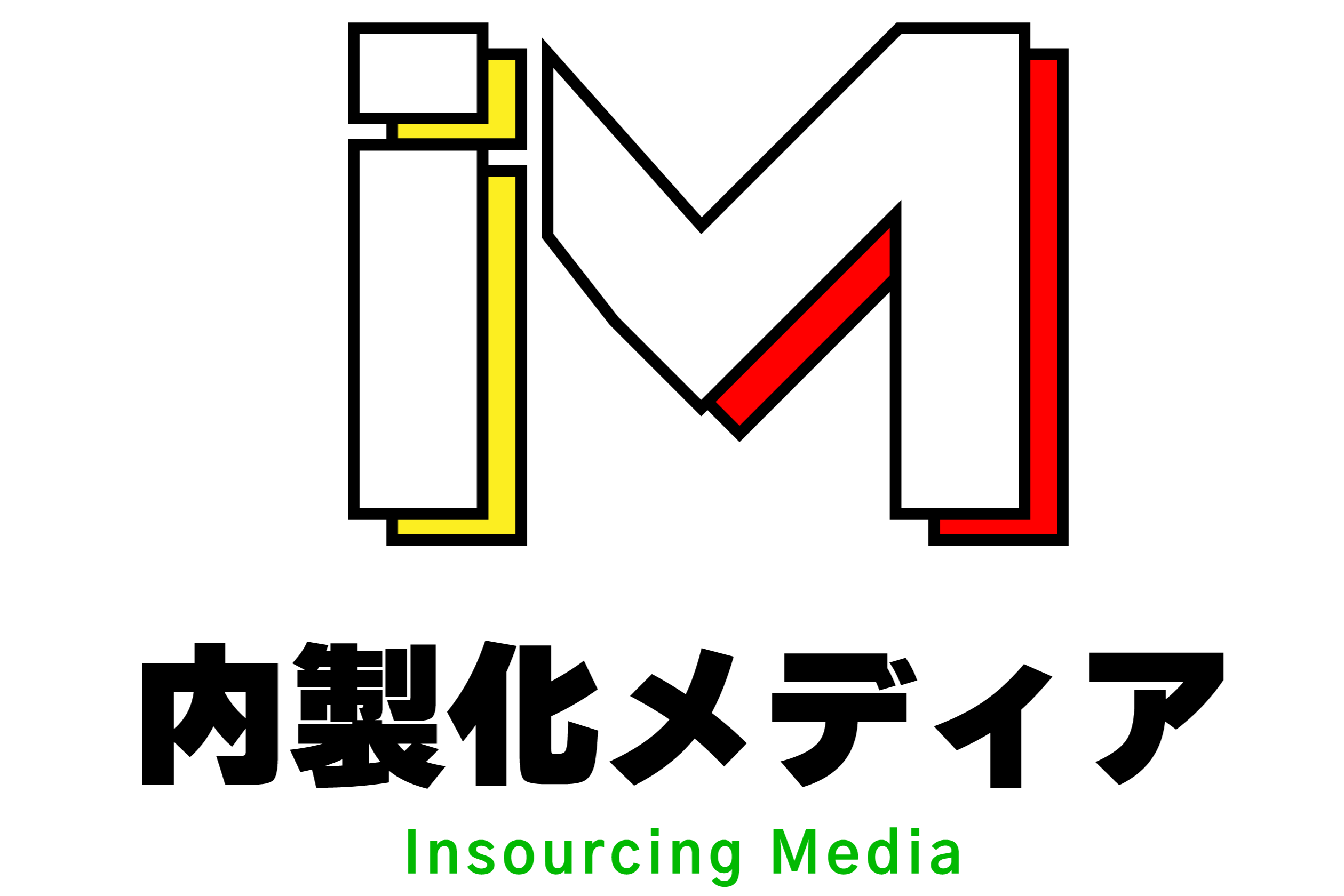
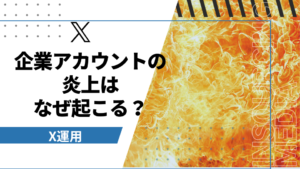



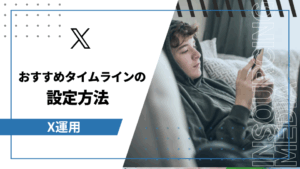

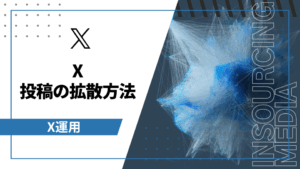
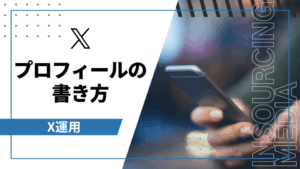
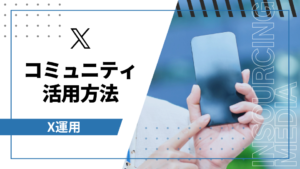
コメント